コラム


元大手食品メーカーグループ企業 代表取締役社長
2024.11.22
「4回ツーアウト、ランナー1・2塁、1点差リードで逆転されそうなピンチ。得点差はわずか1点。あなたがもし監督だとしたら、ピッチャーを交代できますか?」
この問いは、プロ野球の福岡ソフトバンクホークス元監督である工藤公康さんが、あるフォーラムで受講者全体に質問された言葉です。みなさんならどうしますか?
野球をあまり詳しく知らないという方のために、補足しておきたいと思います。
野球ではピッチャー(投手)が初回から登板し、5回を投げ切った時点で、自分のチームが得点をリードしている(勝っている)状況にあると、勝利投手になる権利を得ることができます。
ただ今回のように、あと1アウトの場面で、降板すると勝利投手の権利は得ることができなくなり、勝ち負けはつかず、記録上はほとんどゼロに等しい状況になります。
監督として、このピンチの場面にピッチャーを交代すると、そのピッチャーが得られるかもしれなかった勝利投手の権利を奪ってしまうことになります。厳しい選択の場面ですよね。
さあ、みなさんでしたら、どうします? チームの勝ちを優先するために、ピッチャーを降板させますか? それともそのピッチャーの勝ち星の権利獲得のために、続投させますか?

工藤さんの答えは、「続投」でした。
「実際は変えたい。変えたくて仕方ない、しかし投手にはプライドがある、想いがある。その時に続投させて、仮に打たれたとしても、自分は信頼されている、期待されているという想いから、次の登板に力を発揮することが多い。この場面で投手を変えれば、試合としては勝利に近づくかもしれないが、投手本人の気持ちとしては不満がつのり、モチベーションがあがることは決してない」
監督としての工藤さんが一人ひとりの選手とむきあって、将来を考えながら、長期的に采配をしていることがよくわかりました。
工藤さんの監督時代、試合後の選手にかける言葉はいつも同じだったそうです。勝っても負けても、「お疲れ様、次の一週間、大事にしてね」と声がけをするようです。その言葉を選手がきくと、選手ももう一回チャンスがあると感じ、心の安定にもなり、次の試合への期待にもつながっていくことになります。
私が常日頃、判断の際に大切にしている言葉、「多・長・根」(多面的に、長期的に、根本的に)を実践されているように感じました。
この日のフォーラムは工藤公康さんと、私が日頃、心を込めて取り組んでいる、心身統一合氣道会長の藤平信一さんとの対談形式で進みました。
講演を通じて、工藤さんから学んだリーダーシップは
|
① 選手へのかぎりない愛 |
の3つをポイントとして感じました。
工藤さんいわく、プロ野球の選手はみな個人事業主。自分の結果次第で人生が大きく決まっていく、まさにサバイバルの世界にいます。2軍所属の選手の平均寿命は6年から7年で、1軍所属選手でも約8年程度。そこから引退勧告を受けたあとは、別の世界で生きることがほとんどで、95%以上の選手が野球以外の世界で生きていくことになるのです。
それだけに、個人の成績をいかにあげるかが生き残りに最も大切なことであり、結果をだし続けていく必要がある、まさに厳しい世界だと改めて感じました。
講演会の質問の時間になった時、工藤さんに「リーダーシップで最も大切にされていることは何ですか?」と質問させていただきました。
以前、このコラムでも質問の極意のことをお伝えしておりましたが、まさにその実践をさせていただく機会となりました(極意については、第44回コラム「セミナーを最大限に生かすには?」をご参照ください)。
この講演に向けて、前日から質問をすることは決めていました。100人を超す講演会の場合は、「質問をするんだ」という強い決意がないと、ほぼ質問はできないといっていいと思っています。同じ時を共有するわけですから、より理解していこうと思った場合、質問はおすすめの行動です。
質問しようと考えた場合、想いはその席取りから始まります。後方の席は、質問をする際にはかなり不利なポジションで、質問できない可能性がとても高いです。ただ、日本人は結構遠慮がちなので、前方の席が空いていることがよくありますね。
素晴らしい方がいたらより近くにいくと良い、そうすれば、良いエネルギーをうけることができると言われています。私は素晴らしいエネルギーを受けるためにも、また質問をするためにも、当日はまさに最前列に座り、お話を聞くことにしました。
工藤さんは個人の一人ひとりを最も大切にしていく方で、その選手のためになにができるかを常に考えているそうです。選手の未来のため、いかに行動するかがリーダーにとって、とても大切だと言っていました。
また、選手には練習方法や考え方の選択肢をいろいろ示していきたいと考えているそうです。自分が学ぶことによって、選手に選択肢がふえれば、選手がいろいろと選択し、野球技術を学び、人生をより豊かにしていくことができる。いつもそう考えているそうです。
時々、「忙しい中、いろいろ大変ですね」といわれるが、ご本人いわく、「選手が自分の息子だったらと考えれば、答えは簡単、ずっと考え続けることだってできる」と言っていました。
ほかにも「監督は偉くない。強くする役割、勝つ役割はあるが、偉いわけではない」とも言っていました、その監督という言葉は、そのまま「リーダーとは」に通じるようにも感じています。とても素敵なリーダーシップだと感じています。
またリーダーとして、選手のバックグラウンドをしっかり知ることが大切で、どんな教えられ方をしてきたか、目標はなんなのか? どうなりたいのか? といった一人ひとりのコンテキスト(これまでの環境やそれぞれが置かれた状況といった背景)を知ってから指導していくことが重要だと。
聞くこともとても大切で、よく、「どうなりたい?」「どうしたい?」と常に声がけをしながら、メンバーの状態に想いをよせていたそうです。そのため、選手の歩く姿をみただけで、調子のすべてがわかるそうです。よく見ている証拠ですね。
そしてどうやったら選手がよくなるのかも、いつも考えている。今わからなくても、将来わかってくれればいいと感じているそうです。
さらに、監督としての究極のリーダーシップは、「ドラフト不参加」だといっていました。ドラフトに参加しないということは、新人の指名権放棄となり、当然、その年に新人が入ってこないことになります。結果として、新人が入らないので、現在の選手たちは誰一人クビにならない、つまり戦力外通告を受けないということになるのです。すごい選手愛だと感じました。
現実的には到底無理だとしても、そのような想いを監督が持っていることを知ったとしたら、選手は発奮するでしょうね。FA(フリーエージェント)でお金を積み、次から次へ選手をとろうとしているチームとは正反対の考え方をもっていると感じます。
まさに、選手目線で考えられるリーダーであり、現代にふさわしいリーダー像をみることができました。
これらはある面、ビジネスに通じることがあると思います。
たとえばある営業所を担当している営業課長。営業課全体の成績について責任をもって業務を推進していきます。
そして営業課に担当者5人いれば、5人の評価をみながらビジネス展開していくことになります。ある面、個人をいかしながら、営業課としての成果を追い求めることはチームと選手に置き換えることもできると思います。その時、営業課長として、工藤さんスタイルをつらぬくことはできるでしょうか?

営業課長としては、課全体のパフォーマンスを考えながら、メンバー個人の将来的な成長と、業務上のメンバーの今の成績とを同時に考えていく必要があるということです。
自分の部署にいて好成績をだす社員は、リーダーにとって、とても嬉しい存在です。リーダーとしては、いつまでも自分の課にいてほしいと思うのが、ごく自然な気持ちだと思います。場合によると、そのメンバーを異動させずに抱え込むリーダーがいるのも事実です。もしかすると、将来その人物は企画やマーケティング、その他の部門で活躍できるかもしれないが、自分の課の業績のみを考えるがゆえ、リーダーがその若者の異動をさせず、とどめるケースもあるでしょう。
「そんなことはありえない」と思う方のいる一方、ドキッとされるリーダーもいらっしゃるのではないでしょうか?
メンバーを自分の手元にとどめていくリーダーは、どこを見て判断しているのでしょうか? どのレイヤーで人をみているのか、人を判断しているかということにもつながっていくことになります。
そのメンバー本人の将来を考えれば、決して許されるべきことではないと思いますが、自分の部署に優秀なメンバーを抱え込んでしまうことも、会社でおきている一つの悲劇といえると感じます。
メンバーの成長のため、様々な部署を経験させるのか、一つの部門で徹底的に強化していくのか、様々な考え方があります。大手商社の場合、基本的に最初に配属になった部署に生涯携わっていくことが多いようです。繊維なら繊維、食品なら食品など、専門的に携わっていくと、まさにその業界に精通したプロ中のプロとなります。会社にとってはとても都合のいいことですが、本当の意味では、本人の成長からみた場合はどうなのでしょうか?
私個人は、様々な部署を経験させてこそ、将来的には本人の成長につながり、それが会社の成長にも寄与することになると感じています。
一時的には、人の異動が業績に影響をあたえることもありますが、バランスよく、いろいろな体験をした社員は幅広く、いろいろな視点をもって仕事ができるようになり、結果として、会社のよき判断につながり、本人の成長にもつながることが多いと感じております。
基本的には、「異動、おおいに結構」が私のスタンスです。本人の成長にフォーカスした場合、答えは明らかではないかと感じています。
現代ではリーダーシップのあり方に、「共感」と「共鳴」が求められるようになったと感じます。その先には、大いなる感動があります。
リーダーのあり方に感動し、この人とともにビジョンを達成したい、この人についていきたい、そんな感情がわきでたとき、リーダーシップは本物の輝きをしめすように思います。
リーダーがメンバーに「共感」し、そしてリーダーを含めたメンバー同士が「共鳴」していく、それこそが、これからの組織に求められる要素だと感じています。
▶ back numberはこちら
山本実之氏による「人事担当者を元気にするコラム」の
バックナンバーはこちらからお読みいただけます(一覧にジャンプします)
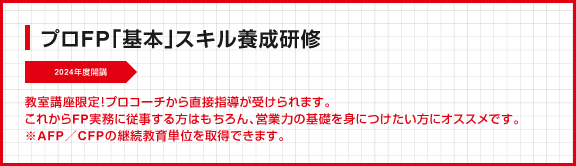
山本実之氏による「プロFPになるためのキャリアデザインの描き方」10月・2月(TAC FP講座)好評お申込み受付中! 詳細はこちら(TAC FP講座のページが開きます)
日本経営合理化協会より、山本実之氏による『「人を動かす」「道は開ける」に学ぶリーダーシップ』が発売されます(下記バナーより日本経営合理化協会サイトの紹介ページにジャンプします)

