コラム


元大手食品メーカーグループ企業 代表取締役社長
2024.07.26
私は現在、心身統一合氣道の稽古を週に2回おこなっています。
ある日のこと、先生が稽古前の話の中で愛ちゃんにむかって、「愛ちゃん、合氣道では受け身において、頭を守ることがとても大切ですね。その頭の中にはなにがある?」って尋ねたのです。
それを横で聞いて、自分だったらどう答えるかな? やはり「脳」だよなって思っていると、愛ちゃんものびやかに「脳」と答えました。私自身も納得です。
ところが先生は「そうだ、愛ちゃんは合氣道の子供クラスからは稽古していなかったねえ」と言うと、また別の女の子、舞ちゃんに尋ねました。
「舞ちゃん、頭の中にはなにがある?」
舞ちゃんがなんて答えたと思いますか? なんと、「夢と希望!」って、笑顔いっぱいで答えたのです。私はびっくりするとともに、なんて素敵な答えだろうと心から思いました。
その時の舞ちゃんには、誰かから言わされているような様子など全くなく、さも当然のように、細胞レベルで叫んでいるように感じました。
なんて、素晴らしい教えなんでしょう。
小さいころから、「頭の中には、夢と希望があるのだ」と感じ、心が満たされていたとしたら、大人になっていろいろなことに出会ったとしても、自分には「夢と希望があるんだ」と、のびやかに頑張れるのではないでしょうか。
そして、なにか課題に立ちあったときでも、「夢と希望」を実現するための試練なのだと、とらえることもできるのではないでしょうか。
私にとって今、この心身統一合氣道の先生の教えは、明治維新のころの適塾や松下村塾のように、人生における生きた学問、生きた学びを身につけさせてくれているように感じています。
とても素晴らしく、今、学校教育に失われているなにかを取り戻しているようにも思います。心身統一合氣道を通じて、教育の本質にふれあっているように感じた瞬間でもありました。
多くの子供たちの頭の中が、「夢と希望」でいっぱいになったとしたら、どんなことが起きていくでしょうか? きっと、いろいろなことにチャレンジしていく子供が誕生していくことだろうと思います。「夢と希望」に満たされていれば、人生を力強く、歩んでいこうとするでしょう。

セルフエスティーム、自己肯定感ともいわれますが、最近はこのセルフエスティームの低い子供が増えているように思います。
やはり、小さいころから比較の中だけで育ってくると、いつも満たされることがないために、自己肯定感を高めることがなかなか難しい環境にあると感じます。
比較されてばかりいると、なかなか自信をもつことが難しいですよね。自分でできないことができるようになっても、それ以上に、もっと上手にできる子たちがいるわけで、「どうせ俺なんて……」というマインドになっても不思議ではありません。比較の中では幸せになれないという、象徴的な考え方だと思います。
特に一般の学校制度の中では、多くの場面において、評価方法が絶対評価ではなく、相対評価になっているため、やむを得ない点もあるのだと感じます。
もしも、武道の昇段や昇級審査のように、あるレベルが設定されていて、それを超えればみんな合格できる、つまり絶対評価になったとしたら、大きく変わっていくことがあると思います。
絶対評価になっていくと、友達はライバルではなく、切磋琢磨していく仲間であり、決して争いあう関係ではなくなると思います。健全な競い合いはあっていいと思いますが、蹴落とすような争い型にはならないでしょう。結果としてお互いが高めあう仲間となっていくことになるでしょう。
2022年のメジャーリーグ、アメリカンリーグで繰り広げられた、ニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手と、ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手の競い合いは見事だったと思います。
あの最高峰の最高の舞台で、お互いがリスペクトしあっている姿、ホームラン王という、ある面でもっとも名誉な賞を争いながらも、お互いに認めあう関係性は素晴らしいと感じます。
大谷選手が「ジャッジ選手のプレーを楽しみにみている」といえば、ジャッジ選手も「大谷選手は素晴らしい選手」とお互いに称えあっている。この関係性からも学べることはたくさんあると感じています。自分だったら、どんな対応をしているかと思うと、この二人のスーパースターの器量に感服します。
ある有名私立一貫校では、成績下位10%の学生を自動的に留年させる、という話を聞いたことがあります。留年に耐えられず、退学する生徒もいるようですが、その中での人間関係はどのようになっているのでしょうか?
友達同士で教えあって、教えた相手の成績が伸びていっても、自分が下位10%に入ってしまえば、留年してしまうという現実。そんな中で、友人同士ではげましたり、教えあったりしていくことはできるのでしょうか? その環境に、真の教育はあるのでしょうか? それは争いそのものであって、切磋琢磨とはかなりかけ離れているように思えます。
現代社会においては、お互いに助け合い、わかちあいながら人生を歩んでいくことが、とても大切に感じます。
会社の評価ではなかなか難しいこともあると思いますが、営業成績などをお互いに絶対評価的に扱うことができたとすれば、メンバー間の成功、お互いの栄光を喜び、わかちあうことができるのではないでしょうか?
評価をチーム制で実施する会社もでてきているようですが、今のように複雑な社会になってくると、より仲間同士で協力しあう関係性が求められていくことだと感じています。
理想論かもしれませんが、絶対評価を導入し、お互いでわかちあい、はげましあうことができれば、結果として、外部の会社と競い合い、戦っていくことができるのだと思います。
大手生命保険会社には「共育事業本部」という部署があると聞きました。「共に育つ」、なんて素敵な考え方でしょう。競争の激しい生命保険業界にあって、共に、そして育っていくという観点をもっていることに、人への期待と、人の輝きを感じます。きっとダイヤモンドのようなキラキラした人財があふれてくるように感じます。
現実、MBO(目標管理制度)を採用している会社でも、一次評価は絶対評価としながらも、二次評価はあきらかなる相対評価になっている会社が多いのではないでしょうか?
ある面、仕方がないとあきらめていますが、本当にそうでしょうか? 絶対評価的に位置づけながらも、結果としては、各部門に相対比率で評価を強く求めている現実。そして、それをやむを得ないと受け入れている部長たち。おそらく多くの会社で起きている現実だと思います。
評価がS,A,Bとあって、それに応じて報酬を可変させるのだとしたら、人件費の予算なども、年度のはじめの段階で、全員がSをとったとしても成り立つように用意していくことはできないでしょうか? その利益体質をベースとして、評価をしていくことなどできないでしょうか?
ある面、やむを得ないところもありますが、武道型の絶対評価軸をクリエイトすることができたとしたら、どうでしょうか? その場合、全員A評価ということもありますし、極端な話、全員がBということもあるかもしれません。
本質的な評価軸をつくることができたとしたら、一定基準をベースとして、評価できるようになったとしたら、メンバー間の協力関係もしっかりと生まれ、自然と「チームとして勝っていこう」という空気感もつくれるのではないでしょうか?
いろいろと課題は多いと思いますが、もしも絶対的価値観に基づく評価軸がもてたとしたら、新しい世界をクリエイトしていけるように感じます。

メンバーの一人ひとりの頭の中に「夢と希望」があったとしたら、会社の中もひかり輝くものになっていくように思います。
だからこそ、多くの子供たちに「夢と希望」を頭の中にもってほしいと感じます。
「頭の中になにがある?」
その問いかけに「夢と希望」と答える子供が一人でも増えていったとしたら、将来の日本は、大きな変化とイノベーションが起きていくように感じています。
人生100年時代、生涯スポーツなども多く叫ばれていますが、武道ももう一度見直されていいと感じています。特に心身統一合氣道は、すべてのビジネスパーソンにおすすめです。心と体を天地とともに一致させていく、そして天地をも味方にしていく、壮大な武道です。
今、ビジネスパーソンで心と体の不一致の方がとても多いと感じます。つまり心身分離の状態ですね。この状態では、個人の仕事だけでなく、リーダーとして人を導いていくことも難しくなっていると思います。
心身統一合氣道は、武道を通じて、心と体を統一するだけでなく、氣をいかすことを学んでいきます。目には見えない氣を、技を通じて、見るというより感じることができるようになります。
AI全盛期にあって、まず追いつけない領域、それが氣の世界だと信じています。戦わない武道であり、導く武道、そして心を練りながら、年を重ねてより強くなっていく武道、それが心身統一合氣道です。
柔道の経験者に聞いたことがありますが、柔道の場合、技を身につけていきながらも、結局は力でもって、若い高校生や大学生に投げられてしまう。それは避けられないと。
しかし合氣道は、年齢をかさね、経験をかさねていけばいくほど、氣が深まるといわれています。死ぬ直前が最も強いという方もいるほどです。
私も心身統一合氣道を通じて、武道家として自己紹介できる日を目指しています。年齢をこえてなにかを目指していくことは、少年のようでいいなと勝手に思っています。
心身統一合氣道では、稽古を始める前に正座をして、全員で前を向いて一礼。そして指導者と向き合って一礼をしながら、「お願いします」と発声します。
最初の一礼は、武道は道につながっていることから、その道への感謝の気持ちを込めてのものです。そして次は、お互い稽古しあう中で、うまくいくときもいかないときもあることから、すべてを含んで「お願いします」と一礼し、はじめていきます。
先人に感謝をし、お互いにリスペクトしながら取り組んでいく姿は、現代社会にも大きく影響を与えていくように感じています。
お互いに礼「お願いします!!」
▶ back numberはこちら
山本実之氏による「人事担当者を元気にするコラム」の
バックナンバーはこちらからお読みいただけます(一覧にジャンプします)
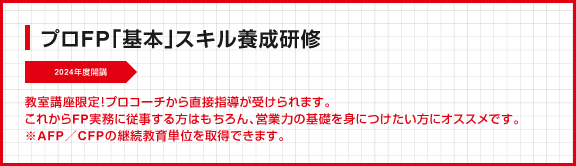
山本実之氏による「プロFPになるためのキャリアデザインの描き方」10月・2月(TAC FP講座)好評お申込み受付中! 詳細はこちら(TAC FP講座のページが開きます)
