コラム


大手食品メーカーグループ会社 代表取締役社長
2023.07.28
「人はなんのために生まれてきたのか?」
そんな疑問をお持ちになったことはありませんか?
思春期になると、疑問に思い始めることの一つのように感じます。
その答えとして、私は「人は幸せになるためにこの世に生を受けた」と思っています。
最近は幸せの研究家のように、幸せについて考えることが多くなり、過去の講演を思い出すことがあります。今から30年ほど前に、妻がヨガを習っていたころのこと、インドの哲人の講演会に参加することになりました。そこで、その哲人から聞いたのが、「2羽の小鳥の物語」です。
ある丘に2羽の小鳥がいました。この2羽は性格が全く異なり、1羽は自分からいろいろ行動し、発信をしていくタイプ。もう1羽は自分の心をしっかりとみつめるようなタイプ。

1羽の小鳥は、自ら幸せや喜びを求めて、いろいろな場所へ飛びまわります。枝から枝へと、いろいろな刺激を求めて移動していきます。次から次へ、どんどんと。
その間、もう1羽の小鳥はというと、ずっと同じ枝にとどまり、目を閉じて空を見上げながら、呼吸を整えている様子。
動く方の小鳥は次から次へと、あいかわらず飛びまわっています。そして、枝から枝へとわたりあるくうちに、ぐるっーとまわって、最後には、もといた枝へと戻ってきました。
その一方で、もう1羽の小鳥はすずしげに空を仰いで、はじめと変わらず、ずっと幸せそうに枝につかまっていた、という話です。
いろいろ経験していきながらも、本当の幸せは足元にあり、自分の心に幸せはあるということを気づかせるような話でもあります。外へ外へと喜びや楽しみを求めてさまよっても、本当の喜びは自分の心の中にあると感じさせる物語といえます。
この話は、以前、聞いたことがある、メキシコの漁師と米国人旅行者の話にも通じるように思います。
それは、メキシコのある小さな漁村でのこと。米国人の旅行者があるボートに近づいていくと、ボートには大きなカジキマグロが釣りあげられ、のせられていました。

米国人は漁師に尋ねました。「何時間くらい漁していたの?」
すると漁師は「そんな長い時間ではないね」と答えます。
米国人は続けて問いかけます。
「もっと漁したら、もっと魚が捕れるだろうね」
「自分と自分の家族が食べるには、もう十分なんでね」
「じゃあ余った時間は何しているの?」
「日が高くなるまでゆっくり寝ていて、それから漁にでる。戻ってきたら子供と遊んで、妻と一緒に昼寝して、夜になったら友だちとワインを飲んで、ギターを弾いているのさ。旦那、することがいっぱいあって毎日結構忙しいんだよ」
すると、米国人の旅行者はまじめな顔で漁師にむかってこう言った。
「バーバードビジネススクールでMBAを取得した人間としてアドバイスするよ。いいかい、君はもっと長い時間、漁をすべきだ。それであまった魚は売る。
そして、お金がたまったら大きな漁船を買う。そうすると、漁獲量は上がり、儲けもふえる。その儲けで漁船を2隻、3隻と増やしていくんだ。やがて大きな漁船団ができる。そうしたら仲買人に魚を売ることはやめだ。
自前の水産加工工場を建てて、そこに魚を入れる。そのころには君は、この小さなメキシコの漁村をでて、サンフランシスコやNYに進出していく。漁獲から加工、販売まで統合して、オフィスビルから企業の指揮をとるんだ」
漁師は尋ねた。
「旦那、そうなるまでにどれくらいかかるんですか?」
「15年から20年くらいだな」
「でそれからどうなるんで?」
米国人は笑って言いました。
「うん、ここからが肝心なんだ。時期がきたら上場する。そして株を売る。君は億万長者だ」
「なるほど。そうなると、どうなるんで?」
「そうしたら、仕事から引退して、海岸近くの小さな村に住んで、日が高くなるまでゆっくり寝ていて、それから漁にでる。戻ってきたら子供と遊んで、妻と一緒に昼寝して、夜になったら友だちとワインを飲んで、ギターを弾くのさ」
この2つの物語から、なにを感じますか?
幸せの本質とはなにか、ということに迫るものがあるように思います。
北鎌倉にある円覚寺(正式には瑞鹿山円覚興聖禅寺といい、鎌倉五山第二位)をご存知でしょうか? その円覚寺の管長である横田南嶺さんと、お会いする機会がありました。将来の仏教界を支えていくに違いない方だと思います。
直接お目にかかるのは2度目となるその日、大手出版社の方とのご縁で、経営者7名で横田管長を囲み、いろいろと問いかけができるとても貴重な会が円覚寺で催されました。
私は、いの一番に質問をさせていただきました。
「人は、みんな幸せになりたいと考えていると思います。幸せになるためにはどのような心構え、どのような考え方でいるといいのでしょうか?」
すると、横田管長は、静かにこう語りました。
「大切なことの一つは『いきち(閾値)』ですね。『いきち』とは、あるレベルをこえると反応してしまう、範囲のことをいうのです。その人にはその人のいきちがあります。ある面、ものごとの考えた方の基準値ともいえるでしょう」
横田管長は続けて、「このいきちが下がると、どうなるか? 朝、起きて幸せ、目がさめて幸せ、食事ができて幸せ、となっていく。仏教とはこのいきちを下げて、限りなくゼロに近づけていく行為そのものなのです」と。
「そしてもし、このいきちが高いと、なにかあってもすべて当たり前。感謝ができずにもっと、もっと刺激を求めていくことになる。結果として幸せから遠のいていく」とお話しくださいました。
そして幸せになるために、もう一つ大切なことは、「心の感度をあげることだ」と言われました。
横田管長はすこし前に、耳が聞こえない方にお会いしたそうです。耳が聞こえないってどんな状況なんだろう、想像がつかない。耳が聞こえないことを考えたら、実は耳が聞こえることはとてもすごいことなんだ、感謝すべきことなんだと、改めて気づかれたそうです。感謝できると、毎日奇跡がいっぱいなんだということに気がついたと。
街でティッシュ配りをしていますね。若手に聞くと、ティッシュは受け取らないといいます。なぜかと尋ねると「いらないから」と。たしかにそうだね。
でも配っている人に想いをよせると、その人には、きっとノルマがあって、受け取ってくれないと仕事にならない。もし受け取ってあげたら、その人は幸せになるよね。だったら受け取ってあげたらいいんじゃない?
「心の感度が敏感になれば、わかるよね?」と言っていました。
たしかに相手のことを考えれば、自然にできることはたくさんあるような感じがします。私たちは相手のことを思う心の感度が低くなっているのかもしれません。
私は会社で、小さな幸せづくりとして実行していることがあります。それはグッドニュースの発表です。定例会の冒頭などに5分程度で実施できるものですが、効果抜群ですよ。
みなさんはどうですか? 日ごろの会議が始まる前にメンバーの雰囲気はいかがですか? 笑顔が消えていませんか? 特に営業関係の会議ですと、予算未達の中で始まる会議はスタートから思いっきり、よどんだ空気感になっていませんか? 始まりの空気を変えていくと、全体の空気感は大きく変わっていきます。
進め方はいたって簡単。まず二人組になって、1分交代で自分のよかった出来事を話し合います。その後、その二人のいい話をメンバー全員で共有します。
その時のポイントは、自分で自分の話をするのではなく、相手から聴いたグッドニュースをみんなに伝えるのです。相手のグッドニュースを伝えるためには、相手の話をよく聴く必要があります。多くの方は、いかに自分が人の話を聴いていないかに気づきます。聴くこと、そのことだけでも人生を明るくしていく力があります。
これを毎月、定例会の前に実施しています。
このグッドニュースを始めようと伝えたとき、「えー、そんないい話ないです」という反応がありました。その後、みなさんにおすすめするときにも、同じような言葉をきくことがあります。でもその時には、こういいます。
「そんなすごくいいことなんて、なかなかないです。でも、たとえば、朝、家族で一緒に食事をしたこと、これってすごいことですよね。だれかが病気で入院していたら、できないことで、当たり前のことではありません。朝日をみた、これもすごいこと、エネルギーにあふれていることも宝物です」と。
私たちは日ごろ、いいことに気づいていないのだということを伝えていきます。

このグッドニュースの目的として、次の3点を伝えています
|
これらの目的をしっかり共有しながら、グッドニュースを実施すると、いろいろと組織に化学変化も起きてきます。
まず笑顔にあふれますね。世の中はネガティブなことがあふれています。会社でも問題解決型会議が多いので、課題から話していくことが多くあることと思います。グッドなことはみんなが笑顔になり、機会発見につながる空気感に包まれます。ぜひトライしてみてください。
また、幸せをとらえるときに、その要素として「地位財」と「非地位財」の2つの考え方があるといわれています。地位財には権力や地位、お金などがあり、特徴的なことは、幸せが一時的なことで長続きしないという傾向のあるものです。非地位財は、愛や友情、つながりなどであり、幸せが長時間続いていくと考えられるものです。
幸せを感じる対象は人それぞれであり、統一される必要は全くないと思いますが、自分が何を追い求めていのか、違いを認識していることは大切だと感じます。
この地位財のみをおっていくと「more and more」の領域にはいり、ひたすら欲望を追い求めるようになってしまい、やがて幸せが去っていく傾向があるといわれています。横田管長の言葉でいえば、「いきち」を上げてしまう行為とも言えるでしょう。
「幸せになること」を決め、人生を歩む中、バランス感覚も求められるものと強く感じます。
▶ back numberはこちら
山本実之氏による「人事担当者を元気にするコラム」の
バックナンバーはこちらからお読みいただけます(一覧にジャンプします)
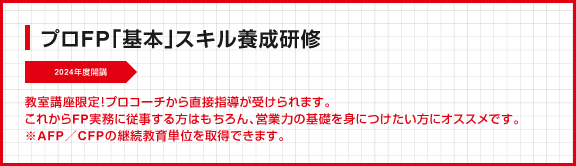
山本実之氏による「プロFPになるためのキャリアデザインの描き方」10月・2月(TAC FP講座)好評お申込み受付中! 詳細はこちら(TAC FP講座のページが開きます)
