コラム


ナトラ合同会社 代表
経営コンサルタント・人財開発コンサルタント
元大手食品メーカー・グループ企業 代表取締役社長
2025.09.26
「君、どない思う?」
この言葉は、松下幸之助さんがよく使っていた言葉だそうです。
経営の神様といわれる人物が発するこの言葉、とても重く、大いなる意味のある言葉だと感じます。
現在、ご縁がありまして、私はその松下幸之助さんが創業したPHP研究所の人財開発コンサルタント、講師となっています。PHPさんは私の憧れの会社でもあり、幼き頃からとてもつながりのある会社の一つです。私の祖父が千葉で事業を起こした際に、松下電器産業グループの販売店にもなっていた関係でもあります。
今思えば、祖父が松下幸之助さんを尊敬していたこともあり、幼き頃から、松下幸之助さんの本に囲まれて、過ごしてきたのだと思います。
人生のメンターである、新将命さんと出会うことになった運命の本『「できる人材」になるための50の法則』もPHPさんからの刊行であることは、決して偶然とは思えませんし、もう一人のメンターである金平敬之助さんとの出会いも、PHPさんの『ことばのごちそう』という本であったことも奇跡的に感じています。
ところで、冒頭の言葉、素晴らしいと思いませんか? すべてわかっていたとしても、「君、どない思う?」と。この問いかけのなかに深い愛情と、メンバーへの期待、関心がこめられている、そんな一言なのだと感じます。
また、関西弁なところもまた、粋に感じる所以であるように思います。
私たちはリーダーとして、どれくらいこのスタンスでいるでしょうか?
メンバーの意見や想いを聴く前に指示をしたり、伝えたりしているのではないでしょうか? 意図的にでもこのような問いかけをしていったとしたら、場の空気は大きく変わっていくように思います。
脳には、問いかけられると答えを探す習性があるといいます。松下幸之助さんのような方に問いかけられたとしたら、その社員の頭の中はフル回転したことでしょう。
その方の成長のためにも、「問いかけること」はとても重要な行動になっていると思います。
よくある「質問」との違いは、真に心から聞いていることと、なにか正解を前提にするのではなく、心から聞いていることであり、それはメンバーの成長にも大きく影響していくように思います。
忙しいという言葉(心が亡ぶという字です)に負けずに、メンバーの日々の成長に思いを寄せ、ぜひ「君、どない思う?」と問いかけてほしいものです。そんな職場、風土ができてきたら、おのずと活気のある職場、会社になっていくのではないでしょうか?
現代のビジネス社会における人間関係には、違和感を覚えることがあります。上司は叱れない、注意そのものがしにくい。上司の方が○○ハラスメントをおそれて行動しにくい。日常において、メンバーも過剰に反応しているようで、「どうなっているの? 日本」と心から感じます。

こう言った、ああ言われた、不快だった、といった次元ではなく、お互いが成長していく、お互いが共通目標をもって共に歩む、共にわかちあうといった観点から取り組むことができないか、真剣に考えています。
人生の多くを費やす会社生活、どうやったらのびやかに、一人ひとりが自分らしく、そして楽しく働いていくことができるかということが、共通目標になっていくように思います。遠慮しすぎず、かといって他人の心の中に土足で入っていけといっているわけでもありません。共通目標のために、お互いが高めあっていく風土があっていいと強く感じています。
そのためには、お互いが尊重しあうことがとても大切です。さわやかなルールなども大切。そして、お互いがほめあうことはもっと大切。一人ひとりが自然体で会話をし、自然体で仕事をすることができれば、心穏やかに業務にむかっていけるのではないでしょうか?
全体で会話をし、励ましあう空気感を共にクリエイトしていく努力も、当然必要になってくると思います。相手に関心を持つ、さらにいえば「相手が関心をもっていることに関心をもつ」、このスタンスであれば、決して、変な空気感になることなく、お互いがお互いに勇気づけ、励ましあうことも可能なんだと感じています。
今こそ心をオープンに、なんでも話し合える環境づくりが必要なんだと思います。
これから伸びる会社と停滞していく会社が真っ二つに分かれてきているように思います。
私は今、独立して、各社の人間関係やリーダーシップづくりを日々支援をしています。そこでポイントになるのは、「のびやかさ」対「閉塞感」です。のびやかな会社にいくと、やはり空気が丸い感じがします。みえない空気に個性がああるかのように思えます。
一方で閉塞感のある会社は、なにか空気が重い、質量が重く感じます。なんとなく、今更ねぇ、という感覚。若者なのに、なにか悟ったような、「どうせ」のような空気感のある会社も見受けます。
やはり、トップが明るい会社、のびやかな会社は社員もいい感じで、イキイキしているように思えます。魚は頭からくさるという言葉は、人間社会でも同じように通じているように思います。
成長というキーワードで人間関係を考えていくと、よくいわれているような「○○ハラスメント」的な要素もすこしは緩和されるようにも思います。
メンバーの成長を心から願う、ほとばしる情熱のような思いで語っていく。
もちろん、昭和の私たちが育ったような環境をすべて、是としているわけでは全くありません。言葉は選ぶものの、今の社会のように、恐れたり、避けたりしている感覚はなんとかしないといけないと、強く感じます。
日本は2040年にはGDPにおいて、インドネシアにも抜かされるといわれています。おそらくはそうなるでしょう。今のこのなんともいえない、お互いに距離をおいている人間関係を継続していたら、そのカウントダウンは前倒しになっていくことだと思います。
経済成長がすべてだというつもりは毛頭ありませんが、経済を通じて、より豊かな社会をこどもたちにつなげていく役割があると感じています。私も教育に第二の人生をかけて、いろいろな場面で伝えています。
この閉塞感のある中で、リーダーはメンバーがどのようなマインドにあるか、どのように接していけばいいのかなど、共に日々、学びあっています。
その中でも冒頭の「君、どない思う?」という言葉には、その関係性をよりよくするメッセージがこめられていると思います。
今、リーダーがメンバーを叱る場面がめっぽう減ったと聞きます。もちろん、なんでも叱っていけばいいわけではありませんが、そのメンバーの成長のためには、どうしても伝えなければならない時があるはずです。しかし現代社会では、そんな場面でも叱ることをさけてしまうことがあるのではないでしょうか?
会社では通常、5年程度でお互いが異動になることを考慮すると、そのメンバーとの接点は2年から3年ほど。多少なにかあったとしても、その期間を耐える? 見過ごす? 結局、どちらかが異動になれば、もう直属の関係になることはまずないわけです。そんな環境であれば、あえてリスクを冒して注意するよりも、放っておけば異動になってしまうよな、と思う人がでてきてもおかしくはないと思います。現実にそんなことが起きているのではないでしょうか?
でもその間に、企業の個人の成長はあるのでしょうか? なんとかしないといけないと強く感じます。私の教育、トレーニングの世界でもなにかできると常に感じております。特に叱ることもそうですが、しかったあとのフォローを特に知らない方が多いと感じます。
この点も松下幸之助さんは天才的だったといいます。
現代において、そのままいうと、まさにハラスメント、一発退場になりますが、時代背景ということを差し引いて、考えていく必要もあると思います。
松下幸之助さんは叱ったあとに、こういったそうです。
「君やったら、やってくれると思っていたんや。今もこれからもずっとやで」
とても素敵な言葉だと思いませんか?
叱ったあとに、「まさに期待していたからいったんだよ」、としっかりフォローしているわけです。いわれた方の心がすっきりと晴れることはないかもしれませんが、俺って期待されていたんだなあと思えただけでも、心は相当変わってくるように思います。
私の父も叱ったあとが、とても上手だったと思います。とても怖く、激しい叱り方をする父でしたが、叱ったあとまでグジュグジュいうところはなく、逆に、単純なことを頼むんですね。
たとえば、「あの新聞記事の何面、きってくれるか?」とか「庭の草をきってくれるか」とかほんとにごく単純なことを頼むんです。
最初、あれだけ叱っていて、なんなのかな? って思うのですが、「やったよ」と伝えると、「おお、きれいにできたなあ。たすかったよ」なんていうんですね。その一言で、わだかまりは一切なくなっていく。今思えば、すごいスキルだと感じます。
私の場合、これが体にしみこんでいたので、会社でメンバーに注意したあとは、すぐになにか簡単なことを依頼するようになっていました。
逆に、依頼することをはじめにみつけておいて、叱ったあとにそのことを依頼するというような余裕の場面をもてることもありました。
事前準備はいつもというわけにもいきませんが、叱ったあとのフォローが大事であることは間違いありません。注意をする方、される方の双方にハッピーとなる事例だと感じています。
このあたりのスキルも、現代に活用できるように思います。
叱りっぱなし、あるいは叱った後もグジュグジュいう、あるいは、今注意していることと、過去を重ねて叱ることはしない等、叱る側のスキルもあげていくことが必要なのでしょう。

現代社会においては、叱るというよりも、注意する、あるいは導くというスタンスの方が適当かもしれません。導くという観点においては、あきらかに目指すビジョンがあり、その方向を指さしながら、さあいこうという想いがあります。
ビジョンや方向性のないところには、指導もなにもないことと感じます。やはり、あたたかなハートフルな想いがベースにあることが指導、育成の根幹をなすことになると思います。
人と人の関係性はとても難しい時代に入っていますが、会社という社会の中で長い時間を過ごしていくので、お互いに理解し、関心をもちあいながら、勇気をもって語る必要があります。そして楽しく過ごせるような工夫も必要になってくると思います。
その中で、リーダーの問いかけがふえる職場、社会になるといいですね。
ともによりよい社会にむかっていきましょう。
さあ、「君、どない思う?」
▶ back numberはこちら
山本実之氏による「人事担当者を元気にするコラム」の
バックナンバーはこちらからお読みいただけます(一覧にジャンプします)
————————————————————————————————
山本実之氏の書籍が2025年9月25日に、PHP出版より刊行されます!
(下記バナーよりAmazonの書籍ページにジャンプします)
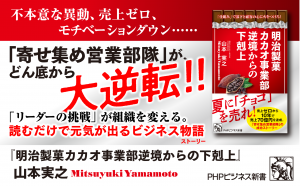
日本経営合理化協会より、山本実之氏による『「人を動かす」「道は開ける」に学ぶリーダーシップ』が好評発売中です(下記バナーより日本経営合理化協会サイトの紹介ページにジャンプします)

