コラム


ナトラ合同会社 代表
経営コンサルタント・人財開発コンサルタント
元大手食品メーカー・グループ企業 代表取締役社長
2025.07.25
もし、あなたが野球をしていたとして、打者として苦手な投手がいたとします。
だれかから、「あの投手はあなたにとって、苦手な投手ですか?」と問いかけられたら、どう答えますか?
「苦手ですね」あるいは、「そんなことはないです。たまたま相性が悪いだけです」等々、いろいろな答え方があると思います。
かつてメジャーリーグで大活躍をされていたイチローさんは、そんな問いに対して次のように答えています。
「いえ、そうではありません。あの投手は自分の可能性を引き出してくれる、素晴らしい投手です。だから私も力を磨いて、彼の可能性を引き出すような打者になりたいですね」
この返答に対して、どう思われますか?
私はこの答えが、困難や苦手なことに対するあるべき姿勢を教えてくれているように思います。また、一見、苦手と思えることに対して、どのような心持ちでいることが好ましいかを示唆してくれているように感じます。
苦手なことを、いやなことだと避けるのではなく、自分の可能性を拓く良い機会ととらえる。これはとても素晴らしい考え方、思考法だと思いませんか?
私たちが仕事において、難しいことや課題に出会ったときはいかがでしょうか? 「いやだなあ」「苦手なことだなあ」ととらえてしまいがちなのではないでしょうか?
すべてのことを良い機会としてとらえていくことは、とても大事だと思います。
いろいろな出来事から「成長」というキーワードにつなげていこうという、前向きな意欲であり、その想いは、人生そのものを豊かにしていくことと感じます。
苦手な事に出会ったときに、「ああピンチだな」と感じる方が多いと思います。
ピンチを日本語に訳すと、最初に出る言葉が「危機」となります。この言葉を分析すると、「危」はたしかに「危険」となりますが、「機」の方はとらえ方を変えると「機会」の「機」とみることもできます。オポチュニティ(opportunity)の「機」とすることもできるということですね。
ピンチはチャンスという言葉があるように、「機」に注目、フォーカスしていくと、一見ピンチに見えることの中に、機会が隠れているということに気づけるのではないでしょうか?
前述のイチロー選手の言葉にも、苦手だと逃げだす前に、その中に機会を見出していく強さ、柔軟性を感じます。

ところで、野球で代打のことをピンチヒッターっていいますが、なぜチャンスヒッターといわないのでしょうね? 代打にでるという場面は、通常、攻撃側からみると、おおいなるチャンスです。なぜピンチヒッターといわれるようになったのか、守備側からみて、ピンチヒッターとなったのか、それはわかりませんが、ネガティブな響きを感じます。ぜひ、チャンスヒッターとして攻撃していくことが望ましいと思います。
私がトレーナーをしているデール・カーネギー・トレーニングでは、いろいろなことへのチャレンジが用意されています。毎回、発表する機会があり、大きなジェスチャーと大きな声で発表したり、行動したりする場面もあり、ある面、チャレンジの連続となります。
受講者は、今までにやったことのないことをしたり、トライしたりすることが多々あり、最初のうちは戸惑うこともありますが、毎回、チャレンジをしていく中で、自分の変化を感じていく場面があります。
そうしたセッションを通じて、ブレークスルーを受講者全員で目指していきます。最初の2~3回は、受講者もなかなか殻を破ることが難しく見えますが、4回、5回とセッションを重ねる中で、一人、また一人とブレークスルーを起こしていきます。そのブレークスルーを目の当たりにすることで、自分自身もチャレンジする勇気がわいてきます。そして、その小さな勇気、自信をみんなで応援することで、自分のものに、自分の力に変えていくのです。
自分一人では、チャレンジできないことでも、同じ仲間同士で支えあって、トライできる環境になっていくのです。
そんな時、トレーナーとして、そしてお互いが受講者として伝えあう大事なメッセージは、「大丈夫、できているよ」ということです。この受け入れられているという感覚を肌で感じることによって、さらに次へとチャレンジしようという想いにつなげることができます。
トライしている最中は、自分の状態がわかりにくいものです。自信をもつことこそが、ブレークスルーのためになにより大切です。お一人お一人は、素晴らしい力をもっているのです。ぜひ自信をもってほしいと考えています。
同時に、苦手なことに接したとき、ピンチに接したときにも、どのようなマインドで対峙していくかがとても大切になってきます。
「大丈夫、いけるよ。大丈夫波動」でとらえていくのか、「ああだめだあ」となげやりになっていくのか、その先にある結果は大きく異なっていくことと思います。その想い、行動が、人生そのものを左右していくことになります。
特に「できない」とか「苦手だ」というような言葉を発していくと、チャレンジする前に、失敗をよびこむような空気感に包まれていきます。言葉そのものが、心や体にも影響を与えていくのです。
実際、その言葉を発しただけで、心が、体が、縮んでいく空気感を感じませんか?
できるだけ回避していきましょう。
冒頭のイチロー選手のようなとらえ方、考え方を身につけていくと、より伸びやかな生き方につながると感じます。この考え方も訓練かなと思います。
日頃の考え方の癖でもあるので、この癖をよい習慣に変えていく努力も、日々の小さな積み重ねによって変革することができることと信じています。
私はトレーナーとして、デール・カーネギー・トレーニングの中で「失敗はない」といつも伝えています。チャレンジすることが素晴らしい。チャレンジできたことで、成功者の一歩を歩んでいる。何度も失敗なんかないと言い切っています。
この失敗という言葉の響きそのものがよくないですよね。辞書から抹消してもいいかもしれませんね。あるのはすべて経験、そして糧になっていくのです。
すべてナイストライ、すべてが学びです。自信をもっていきましょう。
なにか思うようにならないことがあったとしたら、こういいましょう。
「学んじゃったなあ」
そう、すべてが学びです。学びには成長につながる素敵な響きがあると思います。
人生で経験することに、無駄なことはなに一つありません。
今、経験していることの一つひとつが、将来の中で意味をなしていくことになります。今この瞬間にも、未来の人生のドラマが始まっているのです。
そのためにも考え方、マインドが大切になっていきます。
デール・カーネギーのトレーナーとして、とても大切にしていることの一つに「全員を勝者にする、決して敗者として、教室を後にしてはいけない」というメッセージがあります。
デール・カーネギー・トレーニングの中では、毎回、発表をします。その中で受講者にとって、準備した通りに話せなかったり、思った通りに伝えられないことなどもよくあります。そんな時こそトレーナーの腕の見せ所、その人の良いところに思いっきりフォーカスしていきます。
そのレポートの中にも、いいところは必ずあります。そのいいところをしっかり伝えることで、その人を笑顔にする。そして自信をもって、その良さに気づけるようフォローしていくこと、これがとても大事なことです。
その良さをトレーナーとしてしっかりみつけることが大切となってきます。つまり、究極の美点凝視ということにもなります。トレーナーとして徹底的に鍛えられる資質の一つです。
トレーナーのポジティブなフィードバックで、受講者は勇気づけられ、自信を得て次回に臨む。その連続の中で、本当の自信、本当の自分のよさに気づいていくのです。その人の人生そのものが、光を放っていく瞬間です。

いい点をダイヤモンドのように輝かせていく、いいところを導く、トレーナーにとって、最も大切なスキルの一つでもあります。
これはトレーナーだけが求められる資質ではなく、すべてのリーダーに求められる資質なのではないでしょうか?
人の長所と短所は本当に紙一重だと思います。位置や角度、その時のタイミング、どこにフォーカスするかなどによって、変わっていくものだと思います。
リーダーの見方、とらえ方はとても大きいということなのだと感じます。その人の見方によって、苦手なものと位置づけてしまうのか、あるいは成長の糧としていくのか、これは人生そのものの輝きにもつながっていく、大切なことだと思います。そしてこれは、子育てにも通じるように思います。
また、思想の中で、「勝者の思想」と「達成の思想」というものがあります。
企業家であり経営学者の田坂広志著の『人生の成功とはなにか 最期の一瞬に問われるもの』(PHP研究所)の中では、次のように書かれています。
「勝者の思想」とは「競争」が前提となる思想である。そして問題なのは、「勝者になれるのは一握りの人間だけである」こと、「勝者になったとしても、さらなる競争に勝ち続けなければならない」ということである。
そして「競争」の本質は
「誰かが勝者になれば、必ず誰かが敗者になる」
「誰かが何かを得れば、必ず、誰かが何かを
「誰かが喜びを得れば、必ず、誰かが喜びを失う」というもの。
これに対して、「達成の思想」は競争を前提とするものではなく、人生において目標を定め、それを達成することを人生の成功と考える思想です。
言い換えれば、自分にとって価値ある目標を定め、その目標を「達成」することによって成功の喜びを得る思想です。
私は今こそ、「勝者の思想」から「達成の思想」への転換、いや成熟が求められているように感じています。その中では、「喜びの奪い合い」ではなく、まさに「喜びの高めあい」がおこることになります。とても素晴らしいと感じませんか?
だれかがなにかの賞をとったら、みんなが心から「おめでとう」といい、だれかが昇格したら、「よかったね」とお互いに達成を喜びあえる。そんな環境づくりはリーダーにとっても、大切だと思っています。
素直な心で、お互いのよさや達成を心の底から喜び合える、そんな空気づくりを目指していきたいものです。
▶ back numberはこちら
山本実之氏による「人事担当者を元気にするコラム」の
バックナンバーはこちらからお読みいただけます(一覧にジャンプします)
————————————————————————————————
山本実之氏の書籍が2025年9月25日に、PHP出版より刊行されます!
(下記バナーよりAmazonの書籍ページにジャンプします)
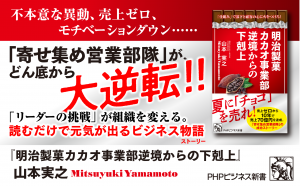
日本経営合理化協会より、山本実之氏による『「人を動かす」「道は開ける」に学ぶリーダーシップ』が好評発売中です(下記バナーより日本経営合理化協会サイトの紹介ページにジャンプします)

