2024年11月時点での雇用関係の助成金まとめ企業で活用できる助成金
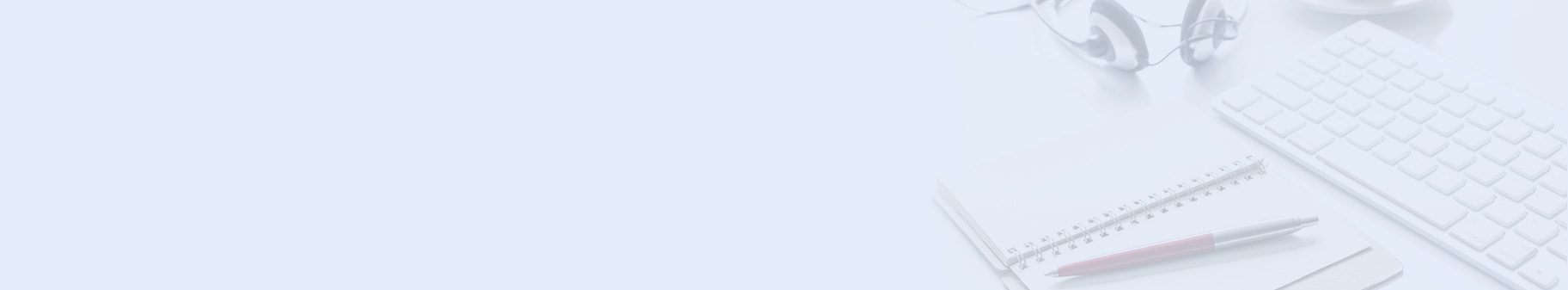
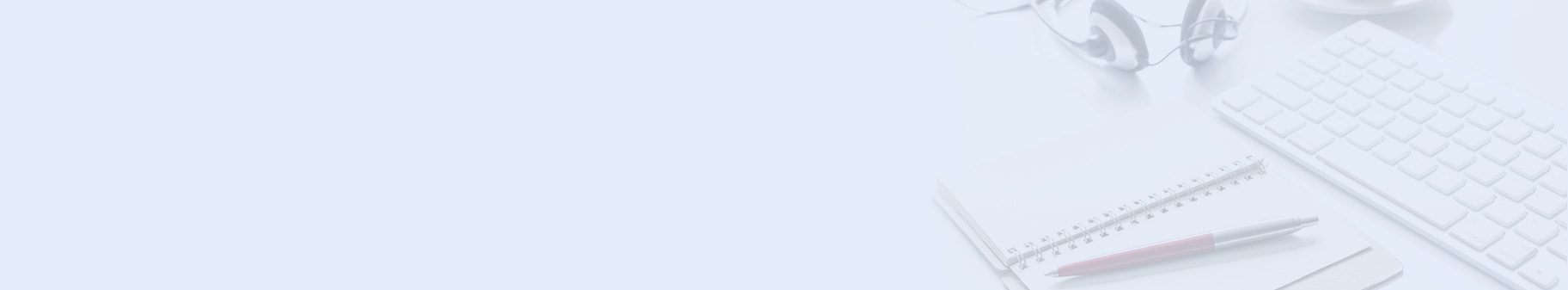
|
助成金とは、企業などが国や自治体へ申請することによって受け取ることができるお金です。社員の採用拡大、人材育成、新規事業への参入等を考えたときに、活用できる助成金はたくさんあります。
*この記事は、2024年11月27日時点の情報に基づき執筆されています。
【目 次】 *クリックでジャンプします
1 助成金申請までの流れ |
|
助成金は、申請して要件を満たしている場合に受け取ることができるものです。
助成金の支給決定までには、厳格な審査が行われます。不正受給の取締りも一層強化されていますので、制度内容をきちんと理解したうえで正しく申請を行いましょう。
また、助成金には、申請要件が細かく決められています。活用したい助成金が見つかったら、まずは会社が申請できる要件を満たしているかを確認しておきましょう。
助成金の多くは、中小企業を対象としたものが多いですが、大企業でも利用できる助成金もあります。また、企業の規模によって助成率が異なるものもあります。 どのような助成金があるかは下記厚生労働省のホームページや、東京都のホームぺージを参照してください。
|
|
ここからは、社内で新たに研修制度を導入する場合に利用できる「人材開発支援助成金」について紹介していきます。 |
|
今回は、人材開発支援助成金の6コースのうち、「人材育成支援コース」「教育訓練休暇等付与コース」「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」について、コース概要と、助成率について紹介していきます。たくさんのコースが用意されていますが、会社が実施していきたい研修内容や研修プランにあったコースを選択していきましょう。主な内容としては次のような分類になっています。
(1) 会社で業務命令として研修・訓練を受講してもらう場合 ❶ Off-JT研修・訓練を行う場合 ❷ Off-JTとOJTを組み合わせて行う場合
(2) 労働者自身が自発的に受講する研修・訓練を支援する場合
① 人材育成支援コース
・概要 10時間以上のOff-JT訓練、新規雇用者向けの訓練、有期契約の労働者を正社員に転換するための研修、訓練などに対して助成が行われます。助成対象となる研修、訓練内容は「人材育成訓練」「認定実習併用職業訓練」「有期実習型訓練」の3種類に分かれており、それぞれの対象者と基本要件は次のようになっています。
なお、人材開発支援助成金の対象となる研修・訓練は、職務に関連した専門的な知識や技能習得を目的としているものです。次のような研修は対象になりません。
【対象にならない研修】 ・職業、職務の種類を問わず、職業人に共通して必要なもの(マナー講習や接遇講習など)
また、研修の実施形式は、人材育成訓練はOff-JT形式によるもの、認定実習併用職業訓練、有期実習型訓練はOJT訓練とOff-JT訓練を組み合わせたもので実施されることとされています。また、e-ラーニングや通信制による研修も対象となります。ただし、一定の要件があり、eラーニング・通信制による訓練の場合は、経費助成のみが対象となり、賃金助成の対象とはなりませんのでご注意ください(後述)。
【参考】厚生労働省 人材開発支援助成金ホームページ
・助成額や助成率 人材育成支援コースの助成額や助成率は次のようになっています。研修を受けた対象者によって助成率が異なります。非正規雇用者を正社員化するために行うものは、経費助成が70%と手厚くなっています。
・賃金要件、資格等手当要件について 2023年4月1日から、従来あった生産性要件が廃止され、賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合に助成額に加算が行われるようになりました。
② 教育訓練休暇等付与コース
・概要 有給の教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が自発的に教育訓練を受講できる環境を作り、教育訓練休暇を実際に取得して、訓練を受けた場合に助成するものです。制度を導入することによって経費助成が受けられ、休暇中の給与の一部も助成対象になります。このコースは下記の3つに分かれています。
このコースでは、就業規則等に教育訓練休暇制度の規定を入れることが必要となります。また、この教育訓練休暇制度において対象となる研修は、事業主(会社)以外の者の行う教育訓練、各種検定またはキャリアコンサルティングとされていて、労働者の方が「自発的に」受講するものが対象となります。会社が実施するOff-JT訓練や、会社の業務命令により受講するものは対象とはなりませんので注意しましょう。
・助成額 教育訓練休暇等付与コースにおける助成額は次のようになっています。2024年4月から長期教育訓練休暇制度の中小企業への賃金助成額が増額になっています。
なお、この助成金は、原則として、新たに長期教育訓練休暇制度を導入する企業が対象ですが、有給で長期教育訓練休暇を取得できるようにする企業は、すでに制度を導入している場合でも対象となります。この場合、通常の支給要件に加え、 ①直近の3事業年度に長期教育訓練休暇制度を適用した被保険者が3人未満であることまたは直近の事業年度に当該制度を適用した被保険者がいないこと。 のいずれかの要件を満たすことで、賃金助成を受けることができます。
③ 人への投資促進コース ⇒ 参照:令和6年度版パンフレット(人への投資促進コース)詳細版(R6.11.5~)
・概要 「人への投資」を加速化するため、2027年3月末までの期間限定で設けられている助成金です。国民からの提案が形になった訓練コースで、現在5つのコースが用意されています。
なお、2024年10月1日から、定額制訓練・自発的職業能力開発訓練(定額制サービスによる訓練)について次のような改正が行われています。2024年10月1日以降に計画届を出すものは新制度が適用されるので、改正後の要件で確認をしてください。
①定額制サービスの助成額の上限額が労働者1人1月あたり2万円に設定されました。
・助成額 人への投資促進コースにおける助成率・助成額は次のようになっています。長期教育訓練休暇制度の賃金助成額が2024年4月1日以降拡充されています。
④事業展開等リスキリング支援コース
リスキリングとは、新たな職業や職種につくための知識や技術の再開発・再教育を行うことで、企業が主体となり、新時代に対応する人材育成支援を行っていく取り組みです。
・概要 事業展開等リスキリング支援コースの対象者や研修の基本要件は次のようになっています。
※ eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等は、標準学習時間が10時間以上または標準学習期間が1か月以上であること。
・助成額・助成率 事業展開等リスキリング支援コースにおける助成率・助成額は次のようになっています。
※eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、定額制サービスによる訓練及び育児休業中の者に対する訓練等は経費助成のみ
事業展開等リスキリングコースで申請を行う際は、新規事業展開等の実施計画もあわせて提出します。 |
|
より多くの企業に助成金を利用して人材育成を進めてもらうために、2024年4月から改正により申請書類の見直しや簡素化、省略が行われています。助成金については、制度改正が頻繁に行われるものなので、助成金の支給申請の際には必ず最新情報を確認しましょう。 4月からの改正点で、大きな点では次のものがあります。 ・Off-JTによる研修をテレワーク勤務中にeラーニング・通信制により実施する場合には、テレワーク勤務を会社の制度として導入し、当該制度を労働協約、就業規則等に規定していることがわかる書類の提出が必要になりました。
eラーニング・通信制により実施される研修・訓練は経費助成のみで、賃金助成の対象にはなりません。また、経費助成の対象となる訓練についても、各訓練メニューの要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。
また、2024年11月5日から、訓練経費の負担の取扱いが明確化されています。 人材開発支援助成金は、会社が社員に訓練を受講してもらい、その訓練経費を会社が全額負担する等の支給要件を満たした場合に、訓練経費の一部等を助成する制度です。これに該当しないものは不支給となります。 申請事業主の教育訓練機関に対する訓練経費の支払が完了しているか否かにかかわらず、申請事業主が、教育訓練機関等から、実施済みの訓練経費の全部又は一部につき、申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む。)を受けた場合や受ける予定がある場合等には、「訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主がすべて負担」したことにはならないため、本助成金の支給対象経費には該当せず、不支給となります。ご注意ください。
なお、2025年度に向けて、現在予算要求が行われています。2025年度の人材開発助成金は、非正規雇用者の訓練機会を増加させるために助成率の拡充や、賃金助成の拡充などが行われる予定です。詳細が公表され次第、改めてお知らせします。 |
|
人材開発支援助成金の申請から助成金を受け取るまでは、次のようになります。
※訓練実施計画届については、基本的には訓練、研修開始の1カ月前までに届出が必要です。
この助成金の最大のポイントは、事前に研修プランを決めて労働局に出しておく必要があることです。先に研修をはじめてしまったら助成金の対象とはなりませんので注意しましょう。 |
|
人材開発支援助成金を利用できるかどうか、導入しようとしている研修が助成金の対象になるものかどうかは、事前に確認をとっておく必要があります。
|
|
助成金は、申請にあたって確認すべき項目も多く、複雑な手続きも多くありますが、正しく利用することで、企業にも、社員にもメリットがたくさんあるものです。本記事で、助成金活用を考えるきっかけになれば幸いです。
*この記事は2024年11月27日時点での内容に基づき執筆されています。
著者Profile 後藤 朱(ごとう・あけみ)
早稲田大学社会科学部卒業。 |