ビジネスに役立つ資格図鑑
【第1回】ITストラテジスト(高度情報処理技術者試験)
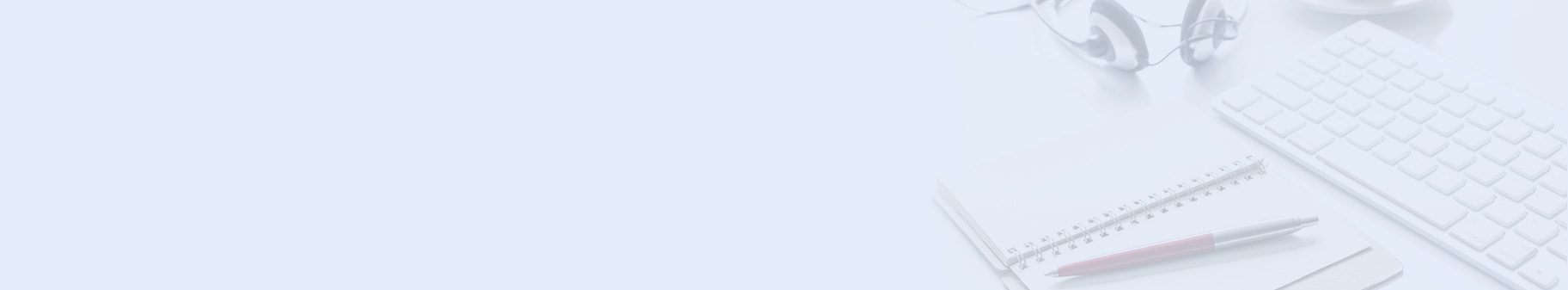
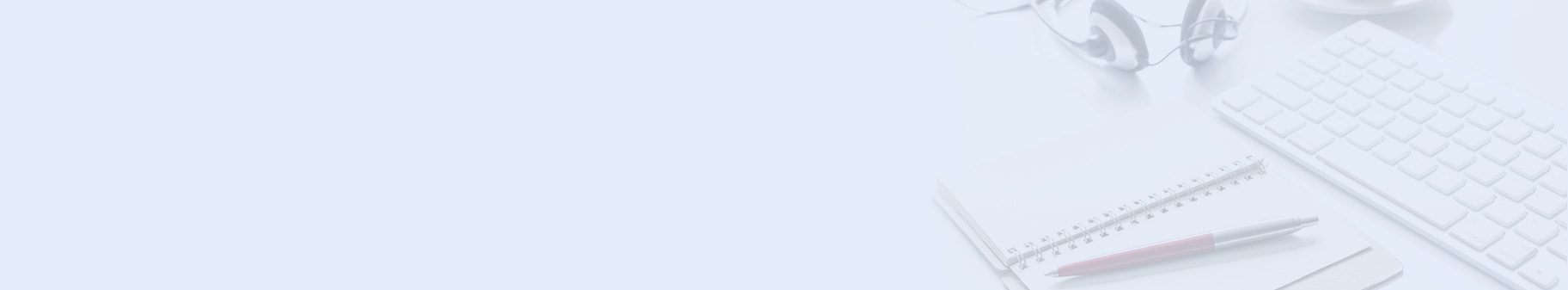

ビジネスに役立つ資格図鑑【第1回】
ITストラテジスト
(高度情報処理技術者試験)
資格の学校TACとして1980年の設立以来、その時々において世の中に必要とされる多くの“プロフェッション”(職業専門家)を養成し、世に輩出してきたTACが、企業における人材育成の場面にスキルセットとして有効な資格をご紹介していきます。
その第1弾は、情報処理推進機構 (IPA)が実施している「情報処理技術者試験」の区分の一つ、ITストラテジスト試験をご紹介します。TACがおススメする理由のほか、実際に活躍する人材の声も掲載していますので、ぜひご覧ください。
|
[Contents:項目をクリックするとジャンプします]
● 資格図鑑スペシャルインタビュー >> ●人材育成のポイント >>
|
 ITストラテジストはITを企業の経営戦略に結び付け、組織の成長と競争力の向上を支援する人材です。ITを活用した経営戦略の立案から、実行までを統括するとともに、IT投資の最適化やリスクマネジメントなども行います。
ITストラテジストはITを企業の経営戦略に結び付け、組織の成長と競争力の向上を支援する人材です。ITを活用した経営戦略の立案から、実行までを統括するとともに、IT投資の最適化やリスクマネジメントなども行います。
このため、経営層とIT部門の橋渡し役となるだけでなく、ITガバナンスの確立や、目標達成に向けたIT戦略の策定を主導することから、企業の効率性向上や新たなビジネスチャンスの創出に貢献する重要な役割を果たしています。
 [インタビュー①]
[インタビュー①]
株式会社クオカード
情報システム部長
菅野 直彦 氏
私が所属する情報システム部は、基幹システムや各種業務システムの企画・開発や運用保守、IT基盤系システムの導入に加え、セキュリティやIT統制の対応といった幅広い業務を担当しています。弊社にはシステム関連の部署がいくつかあり、社外向けシステムなどは他の部署が担当しているのですが、互いにコミュニケーションをとり、常に連携しながら業務を行っています。社内からの様々な問い合わせや相談なども少数精鋭のヘルプデスクでサポートしています。近年、リモートワークが当たり前になったこともあり、関連したセキュリティ周りの対応も増えていますね。
実は私は営業職としてキャリアをスタートさせました。地元の福岡で弊社の親会社に入社し、法人営業や代理店営業、直営店管理などを担当していました。その頃、拠点独自の販売管理システムを構築するプロジェクトが立ち上がり、主担当としてアサインされることになりました。これが私にとって初めてのシステム構築プロジェクトですね。当時25、26歳くらいでしたが、システムの経験は全くありませんでしたので、開発ベンダーの担当者に助けてもらいながら、膨大なタスクを必死にこなしていった記憶があります。導入には大変苦労しましたが、その分達成感もあり、システムを作るのはとても面白いと思いましたね。無事に導入でき運用も落ち着いてきた頃、東京本社で全社システム構築のプロジェクトが発足したこともあり、本社の情報システム部へ異動することになりました。
情報システム部に異動してからは営業時代の実務経験がとても役に立ちましたね。自分が実務で体感した苦労や課題は他の拠点でも同様であることが多く、そういった課題をスムーズに理解し、解決策をシステムの要件に反映することができたと思います。自身のITスキルには少々不安がありましたが、営業現場での経験や、周囲のサポートのお陰で業務を遂行できたと感じています。
そこから現在までに、情報システム部門に20年以上在籍していることになりますね。主に基幹系システムの業務を担当してきましたが、会社合併によるシステム統合や、内部統制対応、人事会計ERP導入、営業基幹システム刷新、BtoB Webサービス構築やBI導入など様々なことを経験させてもらいました。クオカードには2022年に着任しました。
2018年頃のことですが、当時在籍していた親会社の情報システム部で、組織全体の専門性向上を目指し、個々のスキルアップを図る取り組みが始まりました。その一環として資格取得が推奨され、会社として受験費用を補助したり、取得結果を評価に反映させたりするといった方針が決まりました。私は、チームリーダーとしてメンバーに資格の取得を促す立場でしたが、自分が何も資格を持っていなかったら、説得力がないなと思ったのが発端ですね。それまで、資格が無くても業務に支障はありませんでしたが、実務経験だけで得られる知識には限界があると感じていました。自分の視野を広げるためにも何かしなければならないと考えていた時期でもあったので、良いきっかけになったと思います。そういった背景もあり、年始恒例の決意表明の場で「ITストラテジスト試験に合格する」と宣言し、自らやらざるを得ない状況をつくりました。ITストラテジストを選んだ理由はいくつかありますが、国家試験として知名度があり信頼性も高いということが大きいですね。また、幅広い知識を網羅的、体系的に学ぶには、IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)の情報処理技術者試験が最適だと思いました。情報処理技術者試験には様々な試験区分がありますが、せっかくなら最高峰を目指したいという気持ちから、ITストラテジストを選びました。もちろん、自分の業務内容と親和性があるということも選択理由です。
事前の情報収集で、ITストラテジストなどの高度試験に合格するには、午前Ⅰ試験免除を獲得することが有効だとわかったので、まずは条件である応用情報技術者試験の合格を目指すことにしました。また、会社としては全員のITパスポート取得を目標としていたため、並行してITパスポートも取得することにしました。皆と同じ試験区分を自分も受験したことで、実際の難易度を知ることができたのは良かったですね。2018年の秋期試験で応用情報技術者試験に合格したのですが、次のITストラテジスト試験まで1年あいてしまうことや、できるだけ論文試験に慣れておきたいということもあり、2019年春期でプロジェクトマネージャ試験を受けることにし、無事合格することができました。そしていよいよ2019年秋期にITストラテジスト試験に挑戦しましたが、結果は午後Ⅰで不合格。自分なりに準備したつもりでしたが、初挑戦で緊張してしまったのか、試験時間が全く足りませんでしたね。合格には試験に慣れることも重要だと実感しました。その後、2020年秋期のシステム監査技術者試験、2022年春期のITストラテジスト試験に合格することができました。
学習には基本的に参考書と過去問を使いました。学習した知識は自分なりの表現に置き換えノートに整理し、わからない箇所の理解にはYouTube動画なども活用しましたね。紙のノートを使うかは迷いましたが、IPAの試験は手書きなので、その対策も意識し紙のノートを使うことにしました。久々に文具を買い揃えましたが、自分はルーズリーフ派だったなとか学生時代を思い出したりして、少し楽しく感じられましたね。文具の進化にも驚かされました。
資格試験は、努力したことが合格というかたちで明確に目に見えるので良いですよね。受験の緊張感もまた良いものです。大学のキャンパスで丸1日かけて試験を受け、2カ月後の合格発表までどきどきする。そんなことは大人になってなかなか味わえないですよね。
ITストラテジスト試験は、実務経験者で大体150時間から200時間の学習時間が必要といわれています。IPAの高度試験は半年サイクルなので、必要学習時間をそれに割り当てると、おおよそ1日1時間になり、これを目標としました。仕事をしながらまとまった学習時間を確保するのはなかなか難しいですが、たとえば昼休みや通勤中の15分、仕事が終わった後の30分など、そういった時間を合わせると、1日1時間というのは案外簡単に捻出できるものです。ですから土日でまとめて学習するということはあまり行っていません。時間的にも肉体的にも負担が大きいですしね。私はそういった毎日コツコツ勉強する習慣を継続できるように、学習時間をスプレッドシートで管理していました。予め試験日と目標学習時間を設定し、学習の実績を入力することで、進捗状況や残時間がわかるようにしていました。学習を続けていくためには、何かしらモチベーションを保つ術が必要ですが、私の場合、それは全ての学習記録をとって、日々の目標を達成していくことでしたね。この記録は試験後の振り返りにも有効でした。
具体的な学習内容ですが、午後Ⅰは過去問の分析をかなりやりましたね。過去問を解いて、自分の解答と正解との違いやその要因、その解答となるまでの判断プロセスなどを徹底的に分析しました。また、午後Ⅰの問題文と解答文からポイントとなりそうなキーワードを抜き出して、自分なりの辞書を作成し、理解が浅い箇所を重点的に復習していきました。これは、午前Ⅱの対策にもなります。
論文対策については、よく300文字程度の文章をモジュールとして予め作成しておき、いつでも引き出せるようにしておくと良いと言われていますが、私もそうしていましたね。そのモジュールを組み合わせて論文の準備をするのですが、やはり自分の経験に基づいた内容の方が書きやすいので、過去に実施したプロジェクトを題材にした論文シナリオを3つほど作成しておき、それをベースに問題文に合わせて調整する練習を行いましたね。過去問を使って沢山の論文を書きましたが、そのお陰で客観的でわかりやすい言い回しや、指定された文字数で簡潔にまとめる手法を身につけられたと思います。
ITの資格なのに論文は必要なのか?という議論がよくありますが、IT部門でも、何かと文章を書くことは多いですよね。要件定義書や基本設計書はもちろんですが、会社に対する報告書などもあります。組織で働く以上、ドキュメンテーション能力は必要不可欠なものではないでしょうか。私もプロジェクト結果報告書などを作成する機会がありますが、第三者が読んでもわかりやすい表現で、正確にレポートするよう心掛けています。せっかく良い仕事をしても、正しく報告されないことで、正当な評価を受けられないなんてことがあったら、メンバーに対して申し訳ないですからね。そういったトレーニングとしても、論文試験は有効だと感じています。
やはり大きな自信になりましたね。それまでは自己流で業務をしていたところが多かったと思いますが、試験に合格したことで、今までのやり方や考え方が間違っていなかったとお墨付きをもらえた様な気がしました。メンバーを指導する際の説得力も増したのではないかと思います。私が合格したことで、部内から「自分も挑戦してみたい」という人が出てきてくれたのも、うれしい変化の一つでしたね。また、自分が実際に資格試験を経験したことで、自信をもって資格取得を勧められるようになったと思います。
資格について付け加えると、私の場合はこれまでの経験で培ったスキルを再確認する手段として資格を活用しましたが、若手にとっては、資格の学習を通じて未経験の業務を疑似的に体験し、知識やスキルを先取りして得る手段になると思います。キャリアアップの近道にも繋がるのではないでしょうか。資格の教材は網羅的かつ体系的に整理されているので効率よく学べる点も良いですね。このような素晴らしい学習コンテンツがあるのですから、活用しない手はないと思います。
私はITストラテジストとして社内のIT導入に関わるコンサルティング業務も行っていますが、今後注力したいことは、全社レベルでのIT戦略の策定とその推進ですね。私は以前から、情報システム部門にいる以上、CIO(Chief Information Officer:最高情報責任者)を目指したいと考えており、ITストラテジスト取得はそのための一つのステップと位置づけていました。CIOの役割には、経営戦略とIT戦略を結びつけ、企業価値を向上させることが含まれますが、私も将来、そうした役割を果たし、会社に貢献できる存在になりたいと思っています。
ITストラテジストは本当に幅広い知識が得られる資格だと思います。IT戦略やIT企画はもちろんのこと、経営戦略やマーケティング、会計や企業法務なども範囲に含まれますからね。そういった知識があることを示すことができる資格は少ないと思います。それだけに、この資格は、IT担当以外の方にもお勧めだと思います。相手のニーズを的確に捉え解決策を提案する力や、情報を整理し、わかりやすくアウトプットする力の向上に役立つ資格だと思いますね。このスキルは、日常的に必要とされるものですよね。IPAの論文試験では、章立てし、階層や粒度を揃え、客観的かつ論理的に論文を構成する必要があるので、トレーニングとしてとても有効だと思っています。合格することは簡単ではありませんが、何度でも受験できますし、資格試験の学習をすることで日々の業務にも役立つと思いますから、諦めずに挑戦し続けることをお勧めします。
 そのようなITストラテジスト取得者を企業のなかで増やしていくためには、会社がわかりやすく評価してあげるのが一番だと思います。資格取得に取り組むことには、やはりパワーが必要です。苦労して時間を確保し、学習すること自体も評価してあげて欲しいですし、もちろん取得したことについても、きちんと評価していただけると、受験者も取り組みやすいだろうと思います。直属の上司だけでこの取り組みを評価するのは難しい場合もあると思いますので、人事部門の方でもサポートしてあげると良いかなと思います。例えば、会社で推奨する資格を業務や難易度別にリストアップして展開したり、スタッフの資格取得状況を誰でも見られるようにしたりすることが考えられますね。見える化されることで、「だからこういう仕事を任されているのか」といった風に資格の有効性が理解されやすくなると思います。報奨金制度も良いとは思いますが、報奨金獲得が目的にならないよう注意が必要ですね。資格取得に向けた学習や、資格そのものがきちんと実務に活きること、それが結果として評価に繋がっていく仕組みがあるといいと思います。
そのようなITストラテジスト取得者を企業のなかで増やしていくためには、会社がわかりやすく評価してあげるのが一番だと思います。資格取得に取り組むことには、やはりパワーが必要です。苦労して時間を確保し、学習すること自体も評価してあげて欲しいですし、もちろん取得したことについても、きちんと評価していただけると、受験者も取り組みやすいだろうと思います。直属の上司だけでこの取り組みを評価するのは難しい場合もあると思いますので、人事部門の方でもサポートしてあげると良いかなと思います。例えば、会社で推奨する資格を業務や難易度別にリストアップして展開したり、スタッフの資格取得状況を誰でも見られるようにしたりすることが考えられますね。見える化されることで、「だからこういう仕事を任されているのか」といった風に資格の有効性が理解されやすくなると思います。報奨金制度も良いとは思いますが、報奨金獲得が目的にならないよう注意が必要ですね。資格取得に向けた学習や、資格そのものがきちんと実務に活きること、それが結果として評価に繋がっていく仕組みがあるといいと思います。
 [インタビュー②]
[インタビュー②]
オリンパスメディカルシステムズ株式会社
アプリケーションソフトウェア開発
情報支援ソリューション開発 技術開発2
保坂 貴志 氏
現在は、情報支援ソリューション開発部という部署に所属しています。部署としては、内視鏡に関わるAIやITを活用した製品の開発を行っています。医療の分野におけるAIの活用方法としては、病変の発見を支援するような装置で、徐々に世の中に広まりつつあります。
私自身は、製品開発のプロジェクトではなく、そういった製品の先に必要となる標準規格の検討を行っています。ISO(International Organization for Standardization:国際標準化機構)という団体があるのですが、その中でいわゆるISO規格を作る仕事に携わっております。
もともと大学では精密機械を学んでいました。在学中にWindows95が発売になり、IT系のベンチャー企業が沢山立ち上がりました。あの頃はまさにITバブルの絶頂期でしたよね。就職先としてもIT分野を視野に入れて、起業したばかりのITベンチャーでアルバイトをしていました。そこで、もっとITシステムを使った新しいビジネスに関わりたくなり、ITシステムを開発する会社に就職しました。 大手IT企業の関連会社だったのですが、そこで6年間ほどJAVAやUNIXを使った開発業務を担当しました。その後、現在のオリンパスに転職しました。オリンパスに来てからは20年以上勤務していることになります。
転職して来たときに、ちょうどオリンパスは内視鏡を製造・販売している事業の一環で、検査画像をファイリングして、医師がレポートを書くというクライアント・サーバ型のシステムを、全国の病院やクリニックに提供するビジネスを立ち上げようとしていました。そこに私は、システムエンジニアとして参加することになりました。
実際にシステムの導入担当として、病院側が挙げる要件を聞いて実装していくのですが、やはり病院ごとに要件が違っているんですね。それらを一つずつ聞きながらシステムを設計し、導入していくわけですが、導入する案件の数が徐々に増えていくと、全てに対応することが難しくなっていきます。そこで、様々な要件を持つシステムの導入を、もっとうまくコントロールしたいと
思うようになりました。
また、そうなると、「なぜITシステムを導入するのか」と、どうしても病院の運営方針にも関係していくことにも気付き、システムエンジニアというポジションよりも、さらに上段の勉強をしたいなと思いました。それが、プロジェクトマネージャや、ITストラテジストといった高度情報処理分野の資格を学びたいと思ったきっかけです。
もともと業務のなかで関わった技術については資格を取っておこうとチャレンジしてきました。基本情報技術者や応用情報技術者、さらにネットワークスペシャリストと取得していくなかで、情報処理試験のパターンや勉強の仕方を掴んでいくことができました。何度も受けている中で、午前問題は幅広い知識が必要な選択肢問題で、午後問題は問題文を読み込む読解力が必要で、そして最後に論文があって、といったパターンが身に付き、それぞれに対して勉強の仕方が確立してました。
実際の勉強の進め方としては、前半は教科書を読みこんで知識を整理し、後半は過去の出題問題や出版社から出ている問題集を出来るだけ多く解いていくという流れで勉強していました。論文対策としては、自分の経験した業務を振り返り、事前にいくつかの論文を作っておきました。平日は時間の確保が難しかったので、試験勉強は土日に行うといった感じでした。
いまのところ情報処理技術者試験の高度区分では、ネットワークスペシャリスト、データベーススペシャリスト、システムアーキテクト、プロジェクトマネージャ、ITストラテジストを取得しています。過去には、IBMのAIXスペシャリストやJAVAのSJC-Pなどベンダー系の検定試験も取得していました。
それら資格のなかでも、ITストラテジストはエンジニアよりもレイヤーが上の考え方、発想が必要な試験で、勉強していても面白いなと感じました。問題文は様々な業界のプロジェクト事例なので、疑似的にプロジェクトを体験している気分で勉強していました。
取得した資格のなかで、一番影響を受けたと感じているのはやはりITストラテジストです。
他の資格のようなテクニカルなスキルの向上ではなく、ITシステムの導入に対して、外部環境やその事業の見通し、開発計画が、お客様の状況にマッチしているのかを具体的に考える事ができるようになったと感じました。
以前の会社にいたころのお客様との話ですが、ある企業の人事システムの開発を担当することになって、先輩に連れられ要件定義の会議に参加することになりました。するとシステムの開発範囲に、独身寮や社宅の入居者を管理するシステムが含まれていたんです。当時私はまだ20代だったのですが、そのころ既に、寮や社宅を企業が保持するのはもう時代遅れになるという兆候があったので、おそるおそる「そのシステムは必要ですか?」と聞いてみたんです。するとお客様から「うちの会社の歴史を知っているか?」と。その企業は九州の工業地帯に大きな工場を持っていて、そこでは学校や病院といったものまで誘致して工場で働く人たちを集めて来たと。それだけに、うちの会社が従業員に寮や社宅を提供しないという選択肢はないんだよと言われて、なるほどと思いました。また、それと同時にお客様の状況を知らなかったことが恥ずかしくなりました。新人の頃の話ですが、今でも記憶に残っていますので、とても衝撃的な出来事だったのだと思います。そのお客様は、新人の私に企業の歴史を説明してくれて、導入するシステムの必要性を話してくれたわけですが、その時の経験から、お客様の取り巻く環境を踏み込んで理解するという姿勢は、今になっても活きているのだと感じています。
だからオリンパスに転職してからも、病院のシステムを導入するというときに、病院側はどのような想いで、そのシステムを入れようとしているのか、ということを考えるようにしていました。例えば、お客様から「将来は、系列病院の情報を一元管理したいんだよね」という話になった時、やはり技術的な話だけではなく、費用対効果やIT戦略的な話もできなければいけないと思うのです。そういう点では、ITストラテジストの勉強をすることによって、視座を高めることが出来たと思います。
ITの資格取得については、いろいろな考え方があると思います。IT業界は、資格がなくても業務を担当することができてしまいます。ただ、例えばデータベースの設計をお願いしたいといわれた時に、「データベースの設計をしたことありますよ」という経歴とあわせて、「データベーススペシャリストの資格も持っていますよ」と言うことができれば、安心して任せてもらえるようになると思うのです。
小学生の頃からパソコンを触り始めて、自分でプログラムを組んで遊んでいたので、他の学生よりもコンピュータは得意だという自負がありました。しかし、大学時代にITベンチャーでアルバイトしていた頃、そのベンチャーの社長から「お客さんからデータを受け取るためのFTPサーバを立ててよ」といわれたんです。その時は、どうしたら良いかさっぱりわからず、引き受けることさえ出来なかったんですね。やっぱり少しくらいプログラムが組めるというのだけではダメで、ちゃんと仕事に使えるスキルとして身に付けなければ、全く役に立たないのだなと思い知らされました。そういったこともあって、私の場合は、これまで担当した業務の付加価値として、その技術に対応した資格を取っておくようにしてきました。
現在会社の中で担当しているISO規格の開発については、まだ昨年から担当し始めたばかりなのですが、期待されている分野だと思いますので、まずは一歩ずつ頑張って行こうと考えてます。
一方で、私は、一般社団法人 日本ITストラテジスト協会(以降、JISTA)に参画していまして、理事として運営活動に携わっています。JISTAは全国で北海道、東北、関東、中部、関西、中国、四国、九州と8つの支部があって、全体では会員数が1,000人を超える規模の協会になっています。私が所属する関東支部では、毎月様々なテーマで勉強会を開催し、毎年秋には会員以外の方にもアピールする大きなイベントを主催しています。
JISTAは、ITシステムに対して、利用するユーザー側、また提供する側のベンダーや、その間を繋ぐコンサルに従事している方々が入会していまして、立場的にも、企業内で活動している方、独立自営されている方と様々で、同じITストラテジストという資格を持っているものの、立場が全く違う人たちの集まりになっています。毎月開催している月例会では、「テーマ別ディスカッション」というコーナーがありますが、これは、あるテーマについてグループディスカッションを行って、発表しあうという企画です。立場が全然違う人たちが集まって意見交換し、アウトプットすることで、お互いの自己研鑽となり、とても面白い団体だと感じてます。
最近は、若い人もたくさん入会してくれています。経験豊富な先輩方と密な交流ができて、とても面白いと感じてくれているようで嬉しく思ってます。このように、JISTAに入会した会員の皆さんが、JISTAの活動を通して良い知見を得て、自身の業務で活用して更なる活躍に繋げていってもらえるように、これからも運営していきたいと考えてます。
 ITストラテジストは情報処理技術者試験の一つでありながら、テクニカルな資格というよりも、経営層へ提案できるような考え方や視座が得られる資格だと思います。だから、エンジニアからキャリアアップするためのステップとしても良いですし、また、他の職種からIT戦略や経営戦略の業務担当に移るといったキャリアチェンジのきっかけとしても、この資格は利用できると思います。
ITストラテジストは情報処理技術者試験の一つでありながら、テクニカルな資格というよりも、経営層へ提案できるような考え方や視座が得られる資格だと思います。だから、エンジニアからキャリアアップするためのステップとしても良いですし、また、他の職種からIT戦略や経営戦略の業務担当に移るといったキャリアチェンジのきっかけとしても、この資格は利用できると思います。
IT業界は資格を持ってなくても業務はできる、だから取らない、という方もいますが、私は、「この技術をマスターした」という証明のように資格を取得してきました。
情報処理技術者資格は転職の業務経歴書にも書けますので、若いエンジニアの方でもこの資格を上手く活用していけると良いかと思います。
受験資格などは特になく、誰でも受験可能ですが、実務経験が求められる問題が多く、一定の実務経験を持つことが推奨されます。
試験は年に1回、4月に実施されます(ペーパー形式)。試験は、午前2回、午後2回の4部構成で、それぞれ午前Ⅰ、午前Ⅱ、午後Ⅰ、午後Ⅱと4つの試験で構成されています。午前Ⅰは、高度情報技術者試験に挑戦するうえで必要な知識を保有しているかを確認するため、応用情報技術者試験同等の問題が多肢選択式で出題されます。午前Ⅱでは、ITストラテジストに特化した内容から多肢選択式で出題されます。午後Ⅰでは、IT戦略の立案や企業の経営戦略に関する具体的な課題に対して記述式で問われます。午後Ⅱでは、与えられたシナリオに基づき、IT戦略の立案から実行に至るプロセスを論理的かつ詳細に説明する論述式の試験です。
|
試験内容 |
試験時間・出題形式・出題数/解答数 |
|
|
午前Ⅰ |
情報処理技術者として必要となる以下3分野から出題されます。応用情報技術者試験同等のものが出題されます。 |
試験時間:50分(9:30~10:20) |
|
午前Ⅱ |
以下の8分野から出題されます。午前Ⅰと重複する分野もありますが、難易度はあがります。 |
試験時間:40分(10:50~11:30) |
|
午後Ⅰ |
事例問題を通じて実務的な分析力と問題解決能力を評価する記述式問題です。実際の業務で遭遇するようなシナリオから正確に情報を読み取る力、自身の知識を解答に反映させる表現力が必要です。 |
試験時間:90分(12:30~14:00) |
|
午後Ⅱ |
ケーススタディを基にした試験です。戦略的思考と高度な分析力を求められる論述形式で、企業のIT戦略を効果的に実行するための深い理解と実践力が評価されます。 |
試験時間:120分(14:30~16:30) |
合格するためには、各試験で60%以上の得点を獲得する必要があります。特に午後Ⅱの論述試験では、内容の深さや論理性が重視され、経営とITの橋渡し役としての能力が問われます。このため、合格率は約15%程度と、難易度の高い試験だと言えます。
⇒ 試験の詳細につきましては情報処理推進機構(IPA)Websiteの「試験情報:ITストラテジスト試験」にてご確認ください(リンク)
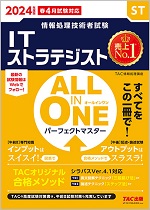 ITストラテジストは、企業の経営戦略とIT戦略を統合し、競争優位を築くためにITを効果的に活用する専門家です。いわば、ICTに関わる司令塔のような役割で、もっとも経営陣に近しい情報処理技術者といえます。この役割を担う人物は、経営の視点とIT技術の深い知識を兼ね備え、ビジネスの目標達成に向けた戦略的思考が求められます。
ITストラテジストは、企業の経営戦略とIT戦略を統合し、競争優位を築くためにITを効果的に活用する専門家です。いわば、ICTに関わる司令塔のような役割で、もっとも経営陣に近しい情報処理技術者といえます。この役割を担う人物は、経営の視点とIT技術の深い知識を兼ね備え、ビジネスの目標達成に向けた戦略的思考が求められます。
ITストラテジストの育成は、企業の競争力向上に直結します。高度なIT戦略を持つことで、業務効率の改善、新規ビジネスモデルの創出、リスク管理の強化などが可能となり、持続的な成長を支援します。ITストラテジストは、デジタルトランスフォーメーションを成功に導くために重要な役割を果たすことが期待されています。
また、彼らは、デジタル技術を活用した業務改革、データ分析、AI導入などの戦略立案と実行をリードすることで、社員の能力を最大限に引き出し、組織全体のデジタル化を加速させます。デジタル化を成功に導くには、ITストラテジストの育成が不可欠であり、社員のリスキリングやDX人材育成への貢献も期待されます。
企業が未来に向けて成長を続けるために、ITストラテジストの育成は重要な投資と言えるでしょう。
TACでは通信教育にて「ITストラテジストコース」と「ITストラテジストWebコース」の2つのコースをご提供していますので、いつからでも学習を開始することができます。もちろん、午前Ⅰ試験が免除される方や午後対策に注力したいという再受験者の方向けのお申込み形態もございますので、安心してご利用ください。
| [通信教育コースのご紹介]*クリックすると各コースの紹介ページへジャンプします ⇒「ITストラテジストコース」のご紹介 ⇒「ITストラテジストWebコース」のご紹介 |
TACの人材育成プログラムにご興味をお持ちいただけましたら、下記「Contact us」よりお問合せください。