ビジネスに役立つ資格図鑑
【第2回】デジタルアクセシビリティアドバイザー
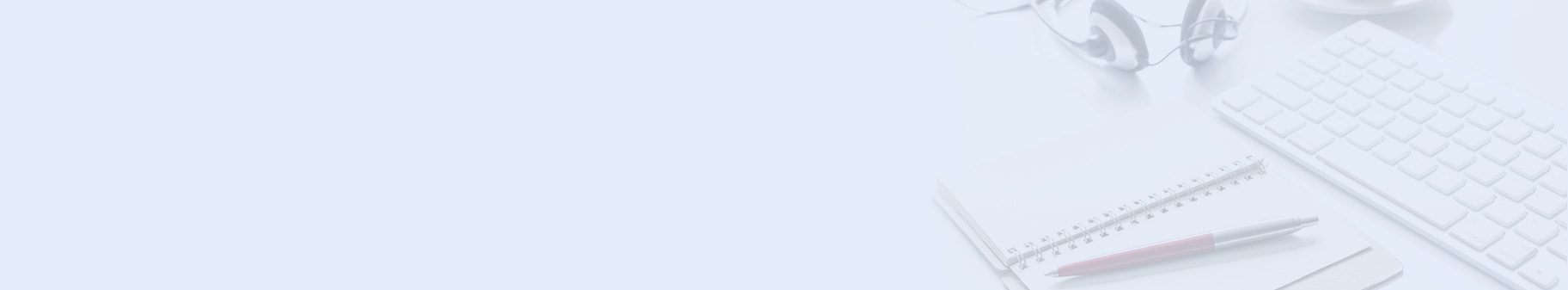
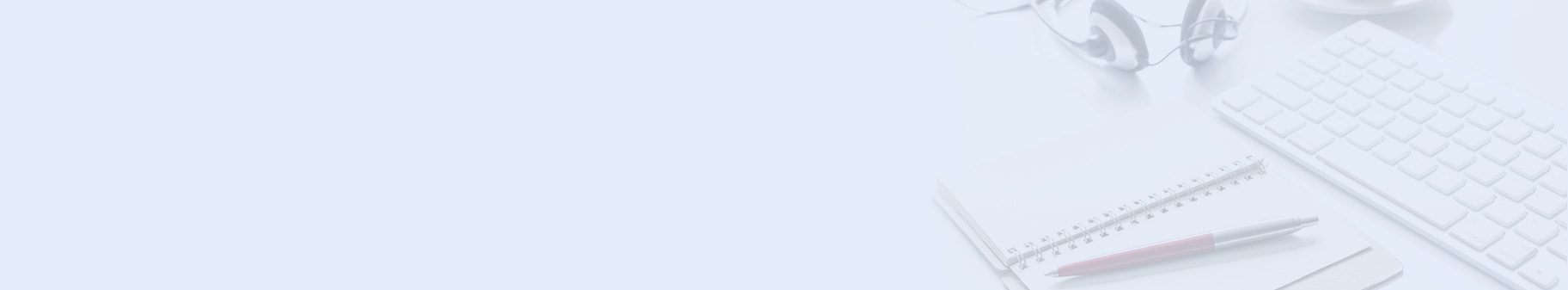

ビジネスに役立つ資格図鑑【第2回】
デジタルアクセシビリティアドバイザー
資格の学校TACとして1980年の設立以来、その時々において世の中に必要とされる多くの“プロフェッション”(職業専門家)を養成し、世に輩出してきたTACが、企業における人材育成の場面にスキルセットとして有効な資格をご紹介していきます。
第2弾は、一般社団法人 日本支援技術協会が実施するデジタルアクセシビリティアドバイザー認定試験をご紹介します。
|
[Contents:項目をクリックするとジャンプします]
● 資格図鑑スペシャルインタビュー >> ●デジタルアクセシビリティアドバイザー認定試験について >> ●人材育成のポイント >>
|
 デジタルアクセシビリティアドバイザー(Digital Accessibility Advisor/略称:DAA)は、一般社団法人 日本支援技術協会が実施する「デジタルアクセシビリティアドバイザー認定試験」に合格することにより取得できる資格で、高齢者や障害者のICT機器利活用をサポートするために必要な障害の理解・技術の理解、アクセシビリティの理解といった基礎的な知識と、デジタルアクセシビリティのマインドを兼ね備えた人材であることを証明するものです。
デジタルアクセシビリティアドバイザー(Digital Accessibility Advisor/略称:DAA)は、一般社団法人 日本支援技術協会が実施する「デジタルアクセシビリティアドバイザー認定試験」に合格することにより取得できる資格で、高齢者や障害者のICT機器利活用をサポートするために必要な障害の理解・技術の理解、アクセシビリティの理解といった基礎的な知識と、デジタルアクセシビリティのマインドを兼ね備えた人材であることを証明するものです。
高齢化社会の進行、障害者差別解消法の改正といったことに加え、企業に対するSDGsへの取り組みやESG経営の推進が求められるなか、デジタルアクセシビリティの重要性は高まるばかりということもあり、企業にとっても注目すべき資格といえるでしょう。
 医療法人社団柏水会 三軒茶屋診療所
医療法人社団柏水会 三軒茶屋診療所
東京リワークセンター
小林 陽香 氏
私は現在、医療法人社団 柏水会の三軒茶屋診療所に併設されている、東京リワークセンターに所属しています。三軒茶屋診療所では心療内科・精神科における外来診療などに対応しているのですが、東京リワークセンターでは主にメンタルヘルス不調によって会社をお休みされていた方が、職場復帰を目指していく際の支援を行っています。
「リワーク」というのは「return to work」の略語ですが、言葉自体はまだそれほど知られてないかもしれませんね。ただ日本でも2000年代から、うつ病などの精神疾患による休職者向けのリワークプログラムが徐々に広まっています。
メンタルヘルス不調により医師から休職を勧められた場合、まずは自宅でゆっくりと回復に専念していただくということになると思いますが、復調したとしても、ストレスが少ない環境で過ごしていたなかから、すぐに職場復帰するのは、本人にとっての負担が大きくなります。「復職準備性」といいますが、ストレス耐性が整っていない状態で職場に戻ると、再発のリスクが高まります。そのとき、間を埋める役割を担うのが「リワークプログラム」だと考えていただけると良いでしょう。
これは処方されるお薬と同様に、自宅療養を経てそろそろ活動量を上げていきましょうというタイミングで医師からの提案があり、本人の同意があって開始します。ただ会社によっては、メンタルヘルス不調からの復職にあたり、リワークプログラムを必須としているところもあります。
東京リワークセンターでは、そういったリワークプログラムを12年ほど前から提供しているのですが、そのなかで私自身は作業療法士として、主に集団プログラムの立案や、担当の方への個別面談等を行っています。
たとえば実際の職場に戻ったあと、業務の開始から終了時間までしっかりと活動ができるのか、注意や集中が続くのか、また眠気といったものが出ないかといったことを確認するために、様々なプログラムを行っていきます。また、プログラムを通してご自身の内省を深めていただくことも目的です。
リワークプログラムの期間は、基本は3~6ヵ月程度となります。それよりも短い期間であったり、逆に1年以上かかるケースもあります。費用は基本的には3割負担となりますが、治療通院を継続する必要がある人のための自立支援医療制度というものがあるので、そちらを使っていただくと1割負担に軽減されます。
このリワークプログラムを経て復職した人は、やはり復職後の再発率は低いと考えられます。少なくとも、その後の復職継続率という視点からみると、やはり、リワークをしていなかった方のほうが、復職継続率が落ちやすい傾向がありますね。
1週間のプログラムが固定化されています。このなかの「セルフモニタリング」というのは、作業を通して認知や行動、気分を観察することが目的です。課題はボードゲームやタイピングのような作業で、誰と、いつまでにやるのか決まっていて、その締め切りまでにすべてを完了してくださいといったような構造です。
運動プログラムもあります。これはうち(東京リワークセンター)の特長だと思うのですが、特にスポーツに力を入れていますね。日頃から外部の体育館を毎週3時間ほどおさえていて、そこでバスケットボールやフットサルなどを実施しています。最初の1時間はダッシュをしたり、筋力トレーニングといった基礎トレーニングにあて、その後の2時間は実際のゲーム(プレー)をするような形ですね。
また、eスポーツも取り入れています。マインドスポーツと呼ばれる麻雀もそうですが、様々なスポーツを「作業」として捉えて実施しています。
こういったプログラムのなかで利用者には、プレイヤーという役割での参加はもちろん、ときに審判や得点集計係など、サポーターの役割になっていただいたり、時には観戦者になっていただいたりします。様々な役割をつくることで、スポーツに関わっていただくということを心がけています。
特にフットサルなどのチームスポーツでは、仕事とのブリッジング(橋渡し)がしやすいといえます。たとえばフットサルであれば「チームで勝つ」という目標に向かって、自分は何をすれば良いのか、何ができるのかを考えていくことになります。自分はフットサルが苦手だけど、相手のパスを邪魔することはできるとか、状況を俯瞰的に見て味方に指示する声を出せますとか、それぞれが得意なところでチームに貢献する、こういったことはビジネスの現場でも置き換えられます。加えて、スポーツが得意ではない方にキャプテンを任せるという場合もあります。これは、仕事上、苦手な業務であっても指示を出したり指摘をする必要がある場面もあるためです。キャプテン以外の場合は、苦手なポジションや役割を任された際の立ち振る舞いを練習することができます。また、体力が持続しない方であれば、途中交代を自分から言い出せるか、SOSを発信できるかといったことは復職後も就労継続していくうえで大事なスキルだと思います。ほかにも、運動プログラムをこなした後、体力を回復させて次のプログラムに参加することができているかといった確認もできます。もちろんスタッフが観察して評価しますが、利用者さんにも課題に直面化し気づきを得ていただくことが目的でもあります。
 そのほか週に1回、ナイトケアがあります。これはフォローアップを目的としたもので、リワークプログラムを卒業した後、たとえば就業後に来られるよう設定していて、16時から20時までの間で実施しています。面談をしたりもしますが、一緒に夕飯を食べたり、ボードゲームや麻雀をしたりといったプログラムを行います。リワークの仲間同士で「最近どう」とか「ちょっと大変でね」、「業務が増えたよ」といった会話をしているのを聞くと、戻る場所があるというのは、役割として大きいかなと感じますね。また、リワークに現在通所されている方がナイトケアを利用することで、復職後のロールモデルに出会うこともできます。
そのほか週に1回、ナイトケアがあります。これはフォローアップを目的としたもので、リワークプログラムを卒業した後、たとえば就業後に来られるよう設定していて、16時から20時までの間で実施しています。面談をしたりもしますが、一緒に夕飯を食べたり、ボードゲームや麻雀をしたりといったプログラムを行います。リワークの仲間同士で「最近どう」とか「ちょっと大変でね」、「業務が増えたよ」といった会話をしているのを聞くと、戻る場所があるというのは、役割として大きいかなと感じますね。また、リワークに現在通所されている方がナイトケアを利用することで、復職後のロールモデルに出会うこともできます。
そういった意味では、リワークをしている方としていない方の大きな違いは、仲間がいるのかというところも大きいように思います。うちではだいたい毎日15人~20人ぐらいでリワークプログラムを実施していますが、毎日顔を合わせていく中で、ピア(peer:仲間)の感覚が醸成されていると思います。
私は作業療法士として、東京都作業療法士会に所属しているのですが、2023年にスポーツ支援委員会というものが設置をされまして、そこに関わる事になったのがスタートですね。スポーツ支援委員会というのは、スポーツに興味を持っているけれど、何らかの理由でスポーツにやりづらさを抱える方々に対する事業に関わったり、そういった支援をすべく活動する作業療法士に対して、様々な情報の提供や支援のために企画をしている委員会です。
身体に不自由のある方がeスポーツにチャレンジするという事業で、やりたいゲームと対象者の困難な点を評価してゲームをできるように工夫や提案をするといった点で、作業療法士として手伝って欲しいという依頼が委員会に寄せられました。ただ私自身は、学校を卒業してから精神分野に就職したので、知識や経験が足りないなと感じていました。そんな時に、東京都作業療法士会の田中勇次郎会長からスポーツ支援委員会に、「こういう資格があるよ」と教えていただいたのが、デジタルアクセシビリティアドバイザー(以降:DAA)でした。紹介動画を拝見し、それをみたところ興味をもちまして、勉強してみようと思ったのがきっかけでした。
まずは公式テキストをしっかり読みこみました。公式テキストの作成には作業療法士の方も携わっていらっしゃるので、考え方や視点等、DAAと作業療法士は似ているところが多いんだなと感じました。そういう意味では、私自身は非常に勉強しやすかったですし、知識も入りやすかったという印象があります。
ただ実際のアクセシビリティという部分については、デジタル技術そのものや、OSごとの違いといった点に私は疎かったので、結構苦労しましたね。私は普段Windowsを使っていますので、Windowsや自分が持っているスマホのOSは、実際に触って、試したりして、覚えることができたのですが、そうでないOSに関しては動画を見るとか、公式サイトで調べるといったような勉強の仕方をしていました。ITとかデジタル機器については苦手とまではいわないものの、得意というほどでもなく、どちらかといえば横文字とかは……という方だったので(笑)。多少、暗記作業のようなところはありましたね。主な機能や目的は同じでも、OSごとに呼び名が違うといったようなところには本当に苦労しました。そこで機能別に表にして、iPhoneではこれ、Androidではこれ、といったような形で覚えていきましたね(笑)。
私の場合、障害を理解するという部分ではもともとの職業柄、知識として持っていたので、障害とITの間を結ぶインターフェースだったり、方法にどんなものがあるかというところを落とし込んでいくという学習スタイルだったと思います。
そうです。Standardの試験項目にはBasicの内容が含まれるとのことだったので、忘れないうちにすぐに受けよう!と思って(笑)。たしか同じ月に受けています。
Basicのときは、どういう問題が出るといった予備知識もなかったのですが、1回落ちてもいいからとにかく受けてみようという気持ちでいました。テキストが届いて、たしか1、2週間くらいで受験してという感じでしたね。それでBasicに合格できて、すぐ2週間後にStandard受けたので、だいたい1ヵ月くらいの間で両方に合格できたと思います。
Basicの方は名称や機能など、単語を覚えるといったところが多かったような印象ですが、Standardになると、テキストが事例集のような内容になっていたので、読むこと自体が自分にとって、知識や経験を増やしていけるような感覚でした。ああ、こういう介入の仕方があるんだなっていう風に感じた覚えがあります。
私自身は勉強や試験というのがそんなに苦ではないというか、嫌いじゃないんです。というのも、ゴールがあって、たとえばこういう問題出るのかな? となると、そのためにどう学習するのか? といったように、目標に照準をあわせて向かっていくというのが楽しく感じたりするタイプなので。考えてみると、DAAの学習中に表を作っていた時も、全然知らない分野だったのでどこか面白く感じていましたね。それに、自分の使っているPCやスマホにもアドオンできる知識だったので、仕事の部分だけでなく、自分のためにもなったなと感じています。
スポーツ支援委員会での業務に直結しているということで取得したこともあって、身体の不自由な方々に対する介入方法だったり、そういった方にとってプラスになる情報を得られたというのはありますね。
また先日、DAAフォーラムでの発表の機会をいただいて、改めて考えるきっかけになったのですが、自分の本業となるリワークでもプラスはあったと思います。メンタルヘルス不調で休職をされた方々は、認知機能が低下するといわれています。記憶力や集中力のほか、処理速度が低下したり、問題解決といった能力も低下する、たとえばメールを見てもどんなふうに返信したら良いかわからなくなる、情報にアクセスできても膨大な量から必要な情報を選ぶことが難しくなるといったことが起こります。そうなると、だんだんとPCやスマホを見るのも億劫になって、触らなくなってしまうといったことになる。こういった形で情報にアクセスする頻度、しづらさというのは、やはり精神の領域でも起こりうることなんです。それは、もともと能力が高かった人たちでも生じています。だからこそ精神領域、とくにメンタルヘルス不調からの復職の分野で働く作業療法士にとっても、このデジタルアクセシビリティという視点は大事だということを、改めて感じましたね。
デジタルやITの知識に関しては、正直にいうと私よりも、リワークの参加者の方が詳しいので、教えてもらうことの方が多いのですが、そういった機器を使った後のこと、たとえば疲労感であったり、苦手意識といったところについては、介入ができるところかなと感じています。
たとえば人事の方との間に共通言語のようなものができるのは、良いことだと思います。打ち合わせの現場などで、認識のズレが生じるといったことはあると思います。そもそもリワーク自体もあまり知られていなかったり、作業療法士という存在も良くわからないということが多かったりするのですが、同じ資格を持っている人同士、同じ言葉が理解できる同士で繋がることができれば、やり取りが早くなっていくのかなという思いはあります。説明をさせていただく時とかに、非常に伝わりやすくなりますから。そしてそれは、復職者にとってもプラスの効果に繋がると思います。
またそれだけでなく、問題や困りごとが起こる前段階、職場で働くことができている段階でリアルタイムに介入できるという手段にもなると思います。休職者が出て、作業療法士が介入するような状況になるよりも、ひょっとしたらその前の段階で未然に防ぐことができるかもしれないですよね。
そういう意味では、人事において復職の窓口になっている方や、ある一定数の人たちがDAAのBasicレベルを持っていたり、職場で受け入れる方々がその知識を持っているということになれば、解決策の幅が広がるのかなと思います。
目標となるゴールが見えない状態だと、いつまでに何をどれくらいやればよいのかわからないと思います。たとえば障害について理解を深めようと思っても、それだけでは何から始めたらよいのかわかりませんよね。そういうときには資格の合格というゴールがあって、そこに向かって勉強していくとか、研修会などに参加することにして、その日に向けて準備していくといった工夫が必要なのかなと思います。
そういったなかで、多くの方がDAAの学習に取り組んでくださって、共通言語が増えていくのはとても良いことだろうなと思います。たとえばその会社で、支援者の方もそうですけれども、会社の中で「デジタルアクセシビリティ」という言葉が当たり前になっていく、浸透していくと、どんどん話もしやすくなるのかなと思います。
また、家族や友達が困っているようなときに「デジタルアクセシビリティ」という言葉や意味を知っていたら良いだろうなとか、身近な人が困っているときに支えあえる知識だと思いますので、ぜひチャレンジしてもらえたらと思います。
 DAAの視点でいうと、機能の名称やそれに関する知識といったものは、勉強すれば身につくし、頭に入ってくるのですが、では実際にそれを使えるのかとなると、そこにはやっぱりギャップがあると感じています。技術はどんどん進化もしますし、新しい機器もどんどん登場します。ですから何か新しい機器、インターフェースなどを見る機会、直接触ることができる機会があったときには、どんどん出向き、自分の体験として頭のなかに入れていかないといけないなと。そうでないと、どんどん風化していってしまうなと感じています。
DAAの視点でいうと、機能の名称やそれに関する知識といったものは、勉強すれば身につくし、頭に入ってくるのですが、では実際にそれを使えるのかとなると、そこにはやっぱりギャップがあると感じています。技術はどんどん進化もしますし、新しい機器もどんどん登場します。ですから何か新しい機器、インターフェースなどを見る機会、直接触ることができる機会があったときには、どんどん出向き、自分の体験として頭のなかに入れていかないといけないなと。そうでないと、どんどん風化していってしまうなと感じています。
実際にIT技術は日々進化していて、より良い機能とか、全く新しい機能が日々出てきます。それはここの利用者の方が復職される現場も同じです。会社に戻る方を支援するわけですから、リワークに携わるスタッフが、社会情勢に疎いとよいプログラムではなくなってしまうと思います。もちろんデジタル技術だけではなく、社会一般の情勢についても情報を集めていきたいです。
ですから医療の資格だけに限らず、たとえば健康経営の勉強や法律関係も含めていろいろな知識を身につけられるよう、勉強していきたいと思っています。
|
[取材日] 2025年1月23日 |
試験は認定レベルにあわせて「Basicレベル」「Standardレベル」「Professionalレベル」の3段階に分けられており、現在は「Basicレベル」「Standardレベル」の試験が提供されています(2025年2月現在)。各レベルで受験資格などは特になく、誰でも受験可能です(「Standardレベル」からの受験も可能)。
試験はCBT方式にて行われており、オデッセイコミュニケーションズの全国約300箇所以上あるテストセンターから都合の良い会場と日時を選んで受験することができます。
■試験の概要
|
|
|
|
|
|
概要 |
地域でICT機器利用を支援・提案するために必要な基礎的な知識や技術を認定 |
業務としてICT機器利用や支援技術を提供する際に必要になるケース別スキルやコーディネートする知識や技術を認定する |
現在は |
|
対象 |
・身近な人を支援する人 |
・業務としてICT機器利用や支援技術を提供する際に必要になるケース別スキルやコーディネートする知識や技術を認定する |
|
|
出題 |
・障害の理解 |
・障害の理解 |
⇒ 試験の詳細につきましては一般社団法人 日本支援技術協会Websiteの「試験のご案内」にてご確認ください(https://daa.ne.jp/exam)
■合格すると
| デジタル認定証であるオープンバッジが授与され、さらに、日本支援技術協会をとおしてデジタル庁が任命するデジタル推進委員になることも可能です。(https://services.digital.go.jp/digital-ps/) |  |
デジタルアクセシビリティアドバイザーは、ICT機器などのデジタル機器を障害のある人や高齢者に対して、その困りに合わせて適切にコーディネートし、その利活用をサポートできる知識と技術をもったスペシャリストであり、これら知識の「スキルセット」を効率的に取得することができる資格試験です。そのため、採用や人材育成に携わる方にとって、非常に有用な知識だといえるでしょう。また、学習により身につく知識は、障害のある人を受け入れる部署のメンバーの方にとっても、よりよい職場環境づくりという点で非常に効果的なものとなり、これは令和6年から民間事業者にも義務化された合理的配慮の提供に役立つ知識と言えるでしょう。
 学習にあたっては、「公式テキスト Basicレベル編」ならびに「公式テキスト Standardレベル編」(ともにエンパワメント研究所のWebsite(https://www.space96.com/)より購入可能)が発売されていますので、こちらを使用して学んでいく形になります。
学習にあたっては、「公式テキスト Basicレベル編」ならびに「公式テキスト Standardレベル編」(ともにエンパワメント研究所のWebsite(https://www.space96.com/)より購入可能)が発売されていますので、こちらを使用して学んでいく形になります。
なお、日本支援技術協会のWebsiteでは、デジタルアクセシビリティアドバイザー認定制度に関心を持っている方のための「DAAコミュニティ」が開設されています。ここでは公式テキストに関連した動画も公開されており、視聴することにより学習効果が期待できます。
[取材協力] 一般社団法人 日本支援技術協会/DAA認定委員会 https://daa.ne.jp/
*当記事に記載されている会社名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーおよびサービス提供元の登録商標または商標です。なお、本文中には™および®マークは明記していません。